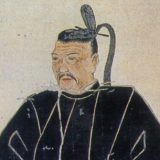九州の大名と言えば、真っ先に名前が挙がるのは島津家でしょう。戦国時代において、「九州の島津家」と言えば最強の家として良く知られています。ゆえに、現代でも島津家の人気は特別に高くなっていますよね。今回紹介する島津貴久は、島津家の15代目当主。島津家は著名な武将が多く、時に誰が何をやったかが分かりにくくなるのですが、貴久は「のちの徳川家康でさえ潰すことができなかった猛将・島津義弘」のお父さんです。島津義弘と言えば、「鬼島津」と呼ばれ、「関ヶ原の戦い」では敵の中を中央突破して撤退したことでも知られる九州最強の武将。その義弘のお父さんですから、もちろん超優秀な人物です。「島津四兄弟」と言われた義久、義弘、歳久、家久の父であり、「九州の英主」と言われる島津貴久についてまとめました。
■父:島津貴久
→島津4兄弟の父・島津貴久の家紋「丸に十文字」を解説|島津家を拡大させた戦国武将
■長男:島津義久
→島津4兄弟の長男・島津義久の家紋「丸に十文字」を解説|九州一の戦国武将
■次男:島津義弘
→島津家次男で九州の猛将・島津義弘の生涯と家紋「丸に十文字」
■三男:島津歳久
→父の貴久や兄の義久、義弘を助けて数々の合戦で活躍した立役者
■四男:島津家久
→島津4兄弟の四男・島津家久の家紋「丸に十文字」を解説|龍造寺隆信を破った戦国武将
スポンサードリンク
|
|
|
島津家の養子になったのに、追い出された貴久
島津貴久は、もともとは島津分家の主・伊作忠良の嫡男として生まれました。そのままいけば島津家を継ぐこともなかったのですが、主家の島津勝久の養子となり、13歳で島津家の15代目当主となります。どうして貴久が島津家の当主になったのでしょう?
それは、島津家の当主が次々と亡くなり、14代目当主となった島津勝久も若くて力がなかったことが原因と言われています。島津家の力が弱まり、家臣たちが離れていくことを懸念した勝久は、分家の忠良を頼って貴久を養子にしました。そして自分は引退し、貴久を当主にすることで島津家を盛り返そうとしたのです。…と言いたいところですが、実は勝久は養子縁組に積極的ではなかったようです。この養子縁組は、勝久よりも島津家の家老たちが推し進めたものだったとか。
少し事情を説明すると、兄から勝久に当主が変わった時、勝久は兄についていた家老を追いやり、自分のお気に入りの家臣を傍におくようになりました。この家臣が、貴久の家・伊作家に近しい人間ばかりだったのです。これが、貴久との養子縁組につながったわけですね。勝久としては、家臣たちに「貴久を養子に」と言われたため、積極的ではないながらも同意したということのようです。
そんな時、島津家のもうひとつの分家にいた島津実久が挙兵。ようは「どうして自分じゃなく、貴久なんかが当主になるんだよ!」という挙兵です。勝久に遠ざけられた先代の家臣たちも、実久の味方をします。これを見た勝久は「貴久じゃなくて実久の味方をすれば、自分がまた権力を握れるかもしれない」と考え、実久の味方に。そして養子縁組を解消し、貴久を追い出してしまいます。
しぶしぶとはいえ、自分から声をかけて養子にしたのに、都合が悪くなったら縁組を解消して追い出す。戦国時代とはいえ、あまりに理不尽な話です。しかし、勝久は結果的に家老とも実久とも関係が悪化し、島津家を追い出されてしまいました。
スポンサードリンク
諦めなかった貴久!再び当主に返り咲き
ところが、この状況でも貴久とその父・忠良はあきらめませんでした。忠良はコツコツと努力を続け、薩摩半島の南にいた「国人衆」と手を結ぶなどして、力をつけていきます。
そして貴久も戦で実久の軍を破るなどの才能を発揮し、鹿児島での勢力をどんどん強めていきます。ここに、島津家を追い出された勝久が現れて再び手を結び(はっきり言って勝手すぎますが)、貴久と実久の戦いが本格化します。…ちなみに、勝久はまた貴久を裏切って実久の方にいこうとするのですが、無視されて大友家のところに逃げています。もとはこの人がすべての発端だったのですが…。
そして、貴久は、実久との戦いに見事に勝利し、薩摩半島を統一して国主になるのです。このあとも混乱が続くものの、のちに朝廷が貴久を正式に「薩摩の国主」と認め、国主を名乗ることになりました。
その後、領土を拡大するために「大隅」という地域を攻めるのですが、戦の最中に亡くなりました。しかし、その意志は息子たちに受け継がれ、嫡男の島津義久が「薩摩」「日向」「大隅」を島津家のものにしています。貴久の成功がのちの島津家繁栄につながったこともあり、父・忠良とともに「中輿の祖」と呼ばれるようになりました。ポルトガルから入ってきた鉄砲をはじめて戦で取り入れるなど、新しいことにも積極的に挑戦した貴久。そんな父の生き方は、子供たちにしっかりと伝わったようです。
スポンサードリンク
島津貴久の家紋とは
島津貴久の家紋は「丸十字紋」。

名前の通り、丸の中に十字架を描いたような形をしている家紋です。この家紋は、平家と戦った島津家の活躍を認めた源頼朝下賜したものと伝えられています。字紋は文字そのものを紋にしたもので、「文字紋」と呼ばれることもあります。字を見ればどんな意味があるのかすぐにわかることや、信仰や縁起に関わるものとして人気の紋でした。一や二などの漢数字が用いられることが多かったのですが、中には名字の一部を図案化したり、二文字用いて図案化するものもありました。珍しい字紋には、縦に一番と描いた一番字、丸に南の字、丸に変形した林を入れた丸に林字、六文字用いた大一大万大吉などがあります。稲葉氏は「隅切り角に角三」、北条氏は「隅立て折敷に二の字」、島津氏は「十の字」、村上氏と八代氏は「丸に上の字」を使用していました。
スポンサードリンク
戦国武将117名の家紋一覧をまとめてチェックしよう
 織田木瓜 織田木瓜 |
 大一大万大吉 大一大万大吉 |
 太閤桐 太閤桐 |
 水色桔梗 水色桔梗 |
| 石田三成 | 豊臣秀吉 | 明智光秀/山県昌景 |
|
 竹に二羽飛び雀/上杉笹 竹に二羽飛び雀/上杉笹 |
 武田菱 武田菱 |
 真田六文銭 真田六文銭 |
 竹に雀/仙台笹 竹に雀/仙台笹 |
| 上杉謙信/上杉景勝/伊達成実 | 武田信玄/武田信繁/武田勝頼/安国寺恵瓊 | 真田幸村/真田昌幸 | 伊達政宗 |
 蛇の目 蛇の目 |
 徳川葵 徳川葵 |
 黒田藤巴 黒田藤巴 |
 向い蝶 向い蝶 |
| 加藤清正 | 徳川家康/徳川秀忠 | 黒田官兵衛/黒田長政 | 大谷 吉継 |
 前田梅鉢/剣梅鉢 |
 一文字三星 一文字三星 |
 池田蝶 池田蝶 |
 足利二つ引き 足利二つ引き |
| 前田利家/前田慶次 | 毛利元就/毛利輝元 | 池田恒興/池田輝政 | 今川義元 |
 丸に立ち葵 丸に立ち葵 |
 九枚笹 九枚笹 |
 二頭立波 二頭立波 |
 二つ雁金 二つ雁金 |
| 本多忠勝 | 竹中半兵衛 | 斎藤道三 | 柴田勝家 |
 丸に竪木瓜 丸に竪木瓜 |
 三つ盛木瓜に剣花菱 三つ盛木瓜に剣花菱 |
 福島沢瀉 福島沢瀉 |
 井伊橘 井伊橘 |
| 滝川一益 | 直江兼続 | 福島正則 | 井伊直虎/井伊直政 |
 鶴丸 鶴丸 |
 丸に細桔梗 丸に細桔梗 |
 丸に七つ片喰 丸に七つ片喰 |
 剣片喰 剣片喰 |
| 森蘭丸/森長可 | 太田道灌 | 長宗我部元親 | 宇喜多秀家 |
 土佐柏 土佐柏 |
 三つ柏 三つ柏 |
 八咫烏 八咫烏 |
 平四つ目結 平四つ目結 |
| 山内一豊 | 島左近 | 雑賀孫一 | 尼子晴久/京極高次 |
 ばら藤に井桁 ばら藤に井桁 |
 丸に違い鎌 丸に違い鎌 |
 蔦 蔦 |
 大友抱き花杏葉 大友抱き花杏葉 |
| 片倉小十郎 | 小早川秀秋 | 藤堂高虎/松永久秀 | 大友宗麟/高橋紹運/立花道雪 |
 中結び祇園守 中結び祇園守 |
 祇園守 祇園守 |
 足利二つ引き 足利二つ引き |
 対い鶴 対い鶴 |
| 小西行長 | 立花宗茂 | 足利尊氏/足利義昭 | 蒲生氏郷 |
 七つ割り隅立て四つ目 七つ割り隅立て四つ目 |
 細川九曜 細川九曜 |
 笹龍胆 笹龍胆 |
 丹羽直違 丹羽直違 |
| 佐々成政 | 細川忠興 細川藤孝 |
源頼朝 | 丹羽長秀 |
 丸に片喰 丸に片喰 |
 榊原源氏車 榊原源氏車 |
 三つ盛り木瓜 三つ盛り木瓜 |
 違い鷹の羽 |
| 酒井忠次 | 榊原康政 | 朝倉義景 | 片桐且元 |
 下がり藤 下がり藤 |
 黒餅 黒餅 |
 北条対い蝶 北条対い蝶 |
 丸に二つ引き 丸に二つ引き |
| 加藤嘉明 | 黒田長政 | 北条早雲 | 最上義光 |
 三つ盛り亀甲に花菱 三つ盛り亀甲に花菱 |
 丸に十文字 丸に十文字 |
 蜂須賀卍 蜂須賀卍 |
 七曜 七曜 |
| 浅井長政 | 島津義弘/島津貴久/島津貴久/島津義久 | 蜂須賀 小六(正勝) | 高山右近/九鬼嘉隆 |
 津軽牡丹 津軽牡丹 |
 北条鱗 北条鱗 |
 丸に上の字 丸に上の字 |
 右三つ巴 右三つ巴 |
| 津軽為信 | 北条氏康/北条氏政 | 村上義清/村上武吉 | 結城秀康/清水宗治/山本勘助/小早川隆景 |
 永楽銭 永楽銭 |
 梅鉢 梅鉢 |
 変わり十二日足 変わり十二日足 |
 丸に三つ引き 丸に三つ引き |
| 仙石秀久 | 筒井順慶 | 龍造寺隆信 | 吉川広家 |
 丸に違い鷹の羽 丸に違い鷹の羽 |
 五七桐 五七桐 |
 生駒車 生駒車 |
 九条下がり藤 九条下がり藤 |
| 浅野幸長/浅野長政 | 豊臣秀次/斎藤義龍/豊臣秀長 | 生駒正俊 | 本願寺顕如 |
 丸に揚羽蝶 丸に揚羽蝶 |
 吾亦紅/地楡に雀 吾亦紅/地楡に雀 |
 丸に三つ葵 丸に三つ葵 |
 輪違い 輪違い |
| 平清盛 | 柳生宗矩 | 松平忠吉 | 脇坂安治 |
 鍋島花杏葉 鍋島花杏葉 |
 結城巴 結城巴 |
 揚羽蝶 揚羽蝶 |
 唐花紋 唐花紋 |
| 鍋島勝茂 | 松平忠直 | 吉川元春 | 陶晴賢 |
 抱き茗荷 抱き茗荷 |
 五本骨扇に月丸 五本骨扇に月丸 |
||
| 堀尾吉晴 | 佐竹義重 |
スポンサードリンク
| 他にもあるぞ!超人気家紋コンテンツ |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |