前田利家は、織田信長から豊臣秀吉に仕えた人物。「豊臣五大老」と呼ばれるほどの活躍をしただけでなく、一代で「加賀百万石」を達成した優秀な武将であることも有名ですね。そんな彼の家紋とこれまでについてまとめました。
スポンサードリンク
目次
|
|
|
織田信長と前田利家
利家は、若いころは派手好きで破天荒な行動が多かったようで、決して評判はよくありませんでした。しかし、そこが「うつけ者」と呼ばれていた信長に気に入られたらしく、信長の小姓として働くことになったのです。お互いによく言われなかった者同士、気が合うところがあったのでしょう、信長は三歳年下の利家をとても可愛がり、利家も信長を主として非常に慕っていたそうです。
信長の目の前で信長の弟を斬首
しかし、利家はちょっとしたもめ事から信長の弟を斬首してしまいました。それも信長の目の前で、です。もちろん信長は激怒し、利家を家から追い出してしまいました。
弟の斬首を信長になんとか許してもらう
利家はこのことを深く反省したようで、信長の「桶狭間の戦い」では信長に許されていなかったにも関わらず参加し、敵の首を討ち取りました。しかし、弟を殺された信長の怒りは解けることがなく、その後の戦で敵の首をとってようやく許してもらうことができました。
信長が亡くなったあとは秀吉に仕える利家
その信長が「本能寺の変」で討たれたあと、利家は織田家の家督争いに巻き込まれることになります。羽柴秀吉と柴田勝家の間で起きたこの争いで、利家は「どっちにつくか」を求められました。どちらとも縁があった利家は、最初は勝家につきその後は秀吉につくという荒業をやってのけます。結果的に秀吉が織田家の実験を握ることになり、利家は以後秀吉のために働くようになります。
スポンサードリンク
秀吉の死後も、利家の影響力は絶大
「豊臣五大老」と言われるまでに秀吉のもとで力をつけた利家は、秀吉の死後もその影響力を維持しています。秀吉が亡くなったのち、豊臣家の中では石田三成とそれに反発する勢力が対立していました。石田三成は人間関係を築くのが苦手だったようで、秀吉の家臣であった加藤清正・福島正則らの彼に対する怒りは非常に大きかったといいます。
三成と秀吉の家臣・加藤清正、福島正則らの仲裁役として活躍
両者の間に立って仲裁をしていたのがこの前田利家でした。秀吉の忠臣でもあり、力もあった前田利家の存在を無視することはできなかったのです。しかし、そのさなかに利家は61歳でこの世を去ってしまいます。
利家亡き後、関ケ原の戦い勃発へ
仲介していた利家の存在がいなくなったことで、力をのばしていた家康をとめられる人間がいなくなってしまいました。そして、家康に加藤清正・福島正則らがついた「東軍」と、石田三成率いる「西軍」の間で「関ヶ原の戦い」が勃発したのです。利家がもう少し長く生きていれば、もしかしたら「関ヶ原の戦い」は避けられたかもしれません。
スポンサードリンク
実は、前田家の領地が100万石になったのは利家の死後?
「加賀百万石を実現した前田利家」と言われていますが、厳密に言うと100万石になったのは利家の死後です。豊臣政権のなかで90万石を得た利家ですが、「関ヶ原の戦い」の前に亡くなりました。100万石になったのは、その「関ヶ原の戦い」で利家の子・利長が家康率いる東軍で活躍し、加増されたために100万石になりました。実は、子供の代でさらに増やして120万石にまでなっています。
家康の次に石高のあった前田家
しかし、こうして石高が増えてよかったことばかりではなく、力があるばかりに常に徳川幕府から監視されていたとか。家康の次に石高がある家ですから、警戒されるのは当然と言えば当然です。前田家は徳川家をたてながら、明治維新で幕府が倒れるまで大名の座を守り抜きました。
前田利家と言えば、奥さんの「まつ」が超有名
前田利家と言えば、本人もさることながら妻の「まつ」がとても有名ですね。「利家とまつ」というタイトルで大河ドラマになったことでもよく知られています。まつは利家との間に11人も子供を産み、さらに秀吉の妻・ねねとも親しく、秀吉と利家の関係が悪くなりそうなときも仲介するなど、とても優秀な妻でした。利家と同じくらいまつは有名な存在で、前田家を語るときには欠かせません。まつは、秀吉が亡くなった後に家康から前田家が疑いをかけられた時も、自分が家康の人質になることで前田家を守っています。その期間、なんと14年。前田家は家康と戦うつもりだったようですが、それで負けていたら今の前田家はなかったので、まつは身を挺して前田家を守ったのです。
加賀梅鉢紋:前田利家の家紋・由来について
加賀梅鉢紋
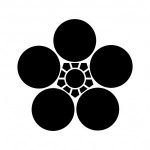
前田利家といえば、「梅鉢紋」ですね。「梅鉢」の家紋は、学問の神様で名高い「菅原道真」がよく使用していた家紋です。利家は、自分のことを「道真の末裔」と宣言してたそうで、その関連から梅鉢紋をよく使用していました。こちらの家紋ですね。梅は、古く中国では菊・竹・蘭と並び四君子の一つとして愛でられました。四君子(しくんし)とは、菊、竹、蘭、梅の4種を草木の中の君子として称えた言葉です。その梅が中国から日本に渡り、春に先駆けて香り高く咲く梅が人々に愛でられるようになりました。万葉集には、梅を詠んだ歌が1位の萩142首に次いで119首も詠まれています。梅の紋様は、奈良時代から用いられていますが、写実的に表現された梅花紋、幾何学的に図案化された梅鉢紋があります。鉢というのは、花の真ん中の雄しべが、太鼓を叩くバチのように見えることから名づけられました。
スポンサードリンク
しかし、この家紋は時代と共に変化したようで、後に前田家では「中央の部分が刀のように見える家紋」を使用するようになっています。
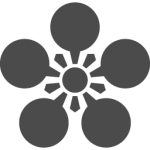
よく↑が前田利家の家紋として紹介されていますが、利家が使用していたのは上の形の家紋で、こちらのものではないので注意しましょう。これは「変形星形の梅鉢紋」と呼ばれています。
秀吉から下賜された五七桐
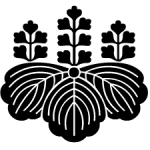
豊臣秀吉の家紋で有名な「五七桐紋」も、前田利家が使用したもののひとつです。秀吉は、自分の家紋を家臣に多く下賜していたことで有名で、「五大老」と呼ばれるほどの忠臣・利家にももちろんこの家紋を下賜していました。日本の硬貨にも使われている非常に有名な家紋ですね。桐は高級木材として、菊紋についで天皇家や功績をあげた者の家紋として用いられました。その風習のはじまりは、後鳥羽上皇から足利尊氏が桐紋を賜ったことです。その後、桐紋が広く広まったのは皇室が臣下へ、下賜された武将が臣下へと付与したことによります。桐紋は桐の葉と花を図案化したもので、一般的には3枚の葉の上に3本の花が描かれ、その花の数によって五三桐、五七桐など呼び名が異なります。豊臣秀吉の家紋は太閤桐と呼ばれ、特定の一つの紋ではなく秀吉の遺品などに確認される桐紋のうち、独自のアレンジが入ったものの総称です。秀吉が家臣に与えたので西日本を中心に多く用いられています。
「菊紋」も使用していた利家

また、利家は「菊紋」も秀吉から下賜されていました。菊紋と言えば、現在では「天皇家が使用している家紋」ですが、この時代にはまだ大名なども使用していたようです。ただ、利家はこの菊紋はあまり使用していなかったようですね。
スポンサードリンク
戦国武将117名の家紋一覧をまとめてチェックしよう
 織田木瓜 織田木瓜 |
 大一大万大吉 大一大万大吉 |
 太閤桐 太閤桐 |
 水色桔梗 水色桔梗 |
| 石田三成 | 豊臣秀吉 | 明智光秀/山県昌景 |
|
 竹に二羽飛び雀/上杉笹 竹に二羽飛び雀/上杉笹 |
 武田菱 武田菱 |
 真田六文銭 真田六文銭 |
 竹に雀/仙台笹 竹に雀/仙台笹 |
| 上杉謙信/上杉景勝/伊達成実 | 武田信玄/武田信繁/武田勝頼/安国寺恵瓊 | 真田幸村/真田昌幸 | 伊達政宗 |
 蛇の目 蛇の目 |
 徳川葵 徳川葵 |
 黒田藤巴 黒田藤巴 |
 向い蝶 向い蝶 |
| 加藤清正 | 徳川家康/徳川秀忠 | 黒田官兵衛/黒田長政 | 大谷 吉継 |
 前田梅鉢/剣梅鉢 |
 一文字三星 一文字三星 |
 池田蝶 池田蝶 |
 足利二つ引き 足利二つ引き |
| 前田利家/前田慶次 | 毛利元就/毛利輝元 | 池田恒興/池田輝政 | 今川義元 |
 丸に立ち葵 丸に立ち葵 |
 九枚笹 九枚笹 |
 二頭立波 二頭立波 |
 二つ雁金 二つ雁金 |
| 本多忠勝 | 竹中半兵衛 | 斎藤道三 | 柴田勝家 |
 丸に竪木瓜 丸に竪木瓜 |
 三つ盛木瓜に剣花菱 三つ盛木瓜に剣花菱 |
 福島沢瀉 福島沢瀉 |
 井伊橘 井伊橘 |
| 滝川一益 | 直江兼続 | 福島正則 | 井伊直虎/井伊直政 |
 鶴丸 鶴丸 |
 丸に細桔梗 丸に細桔梗 |
 丸に七つ片喰 丸に七つ片喰 |
 剣片喰 剣片喰 |
| 森蘭丸/森長可 | 太田道灌 | 長宗我部元親 | 宇喜多秀家 |
 土佐柏 土佐柏 |
 三つ柏 三つ柏 |
 八咫烏 八咫烏 |
 平四つ目結 平四つ目結 |
| 山内一豊 | 島左近 | 雑賀孫一 | 尼子晴久/京極高次 |
 ばら藤に井桁 ばら藤に井桁 |
 丸に違い鎌 丸に違い鎌 |
 蔦 蔦 |
 大友抱き花杏葉 大友抱き花杏葉 |
| 片倉小十郎 | 小早川秀秋 | 藤堂高虎/松永久秀 | 大友宗麟/高橋紹運/立花道雪 |
 中結び祇園守 中結び祇園守 |
 祇園守 祇園守 |
 足利二つ引き 足利二つ引き |
 対い鶴 対い鶴 |
| 小西行長 | 立花宗茂 | 足利尊氏/足利義昭 | 蒲生氏郷 |
 七つ割り隅立て四つ目 七つ割り隅立て四つ目 |
 細川九曜 細川九曜 |
 笹龍胆 笹龍胆 |
 丹羽直違 丹羽直違 |
| 佐々成政 | 細川忠興 細川藤孝 |
源頼朝 | 丹羽長秀 |
 丸に片喰 丸に片喰 |
 榊原源氏車 榊原源氏車 |
 三つ盛り木瓜 三つ盛り木瓜 |
 違い鷹の羽 |
| 酒井忠次 | 榊原康政 | 朝倉義景 | 片桐且元 |
 下がり藤 下がり藤 |
 黒餅 黒餅 |
 北条対い蝶 北条対い蝶 |
 丸に二つ引き 丸に二つ引き |
| 加藤嘉明 | 黒田長政 | 北条早雲 | 最上義光 |
 三つ盛り亀甲に花菱 三つ盛り亀甲に花菱 |
 丸に十文字 丸に十文字 |
 蜂須賀卍 蜂須賀卍 |
 七曜 七曜 |
| 浅井長政 | 島津義弘/島津貴久/島津貴久/島津義久 | 蜂須賀 小六(正勝) | 高山右近/九鬼嘉隆 |
 津軽牡丹 津軽牡丹 |
 北条鱗 北条鱗 |
 丸に上の字 丸に上の字 |
 右三つ巴 右三つ巴 |
| 津軽為信 | 北条氏康/北条氏政 | 村上義清/村上武吉 | 結城秀康/清水宗治/山本勘助/小早川隆景 |
 永楽銭 永楽銭 |
 梅鉢 梅鉢 |
 変わり十二日足 変わり十二日足 |
 丸に三つ引き 丸に三つ引き |
| 仙石秀久 | 筒井順慶 | 龍造寺隆信 | 吉川広家 |
 丸に違い鷹の羽 丸に違い鷹の羽 |
 五七桐 五七桐 |
 生駒車 生駒車 |
 九条下がり藤 九条下がり藤 |
| 浅野幸長/浅野長政 | 豊臣秀次/斎藤義龍/豊臣秀長 | 生駒正俊 | 本願寺顕如 |
 丸に揚羽蝶 丸に揚羽蝶 |
 吾亦紅/地楡に雀 吾亦紅/地楡に雀 |
 丸に三つ葵 丸に三つ葵 |
 輪違い 輪違い |
| 平清盛 | 柳生宗矩 | 松平忠吉 | 脇坂安治 |
 鍋島花杏葉 鍋島花杏葉 |
 結城巴 結城巴 |
 揚羽蝶 揚羽蝶 |
 唐花紋 唐花紋 |
| 鍋島勝茂 | 松平忠直 | 吉川元春 | 陶晴賢 |
 抱き茗荷 抱き茗荷 |
 五本骨扇に月丸 五本骨扇に月丸 |
||
| 堀尾吉晴 | 佐竹義重 |
スポンサードリンク
| 他にもあるぞ!超人気家紋コンテンツ |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |


