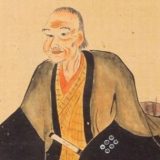豊臣秀長は、豊臣秀吉の弟にあたる人物です。兄の秀吉があまりに有名なために、秀長にはあまりスポットが当たらないのですが、彼は「豊臣家の運命を握る、とても重要な存在」といっても過言ではありません。「秀長がもっと長く生きていれば」。後世でもそう言われるほどの人物・豊臣秀長についてまとめてみました。
スポンサードリンク
目次
|
|
|
秀吉と仲のいい兄弟であった秀長

戦国時代において、兄弟は時に敵になることも多いのですが、秀吉と秀長は違いました。秀吉はもともと農民の出身で家を出ており、その後は弟の秀長と長く会っていません。
戦国時代には珍しい兄弟愛
二人が再会したのは、秀吉がねねと結婚した当たりのことと言われていて、離れてから10年以上の時が経っていたと言われています。にも拘わらず、秀長は兄のいうことをよく聞き、家臣にもなり、豊臣家を支えるようになりました。戦国時代には珍しい兄弟愛ですね。秀吉も、農民出身で後ろ盾がなかったことから、弟の秀長のことは特に頼りにしていたようです。自分が城をあけるときは秀長に留守を任せるなど、何かと秀長を頼りにしていました。
スポンサードリンク
信長からも認められ、豊臣秀次とも関係が良かった秀長
この秀長、秀吉の主だった織田信長にも気に入られるほどの逸材でした。秀吉が同行することができなかった「長島一向一揆」も、信長に同行しているくらいですから、かなり信頼されていたことが分かります。秀長はとても温厚な人柄で、誰に対しても誠実に接したようなので、そういうところが信長も気に入ったのでしょう。
秀吉の四国攻めは秀長の指揮だった
また、秀吉が行った「四国攻め」は、実は秀長の指揮によるものです。四国を統一した長曾我部元親と戦うための「四国攻め」でしたが、秀吉はこの時病に臥せっていたため、かわりに秀長が軍を率いたのです。結果はご承知の通り。元親は土佐(高知)以外の3つの国「阿波(徳島)」「讃岐(香川)」「伊予(愛媛)」を失いました。四国攻めは秀吉の天下統一に欠かせないものでしたので、秀長は秀吉の天下統一に大きく貢献したことが解ります。
連戦により体調を崩す秀長
ところが、いくつもの戦に関ったことが良くなかったのか、秀長はたびたび体調を崩すように…。秀吉が天下統一を賭けておこした「小田原征伐」には、同行していません。この時、体の具合は相当良くなかったようです。そんな秀長を心配して、秀吉の養子・豊臣秀次(秀吉の姉の子)も神社に出向いて「病気が良くなるように」とお願いしたそうです。秀長は秀次とも関係が良く、豊臣家の人間関係を良いものに保つ存在でもあったのです。
その秀長の死~豊臣家の斜陽
多くの人の願いも届かず、秀長は51歳でこの世を去ります。いつ死ぬか解らない戦国の世の中で、51歳まで生きたというのは決して短い人生ではありません。しかし、秀長の死はその後の豊臣家に暗雲をもたらしました。秀長の支えがなくなった秀吉は、その後に非道な行いをするようになります。
秀長の死後、非道な行為をした秀吉
有名なのは、秀次の切腹ですね。諸説あるものの、秀次を切腹させたのは後に生まれた嫡子・豊臣秀頼に家督を相続させたかったためと言われています。この秀次切腹の事件で、秀吉は秀次の妻子に至るまで惨殺し、穴を掘っただけのところに遺体を投げ込むという非道なことをしました。
英次の妻になる寸前だった駒姫も殺害する秀吉
この惨殺された女性の中に、秀吉に請われて秀次の妻になろうとしていた駒姫もいました。駒姫はまだ秀次に会ってもおらず、父の最上義光がほうぼうを駆け回って「命を助けてくれ」とお願いしていましたが、無残にも殺されてしまいます。この所業は各大名にも伝わり、豊臣家ではなく徳川家康に傾く人間を増やしてしまいました。
スポンサードリンク
朝鮮出兵も秀長の死後の出来事
また、有名な「朝鮮出兵」も秀長の死後に行ったことです。正確に言うと、秀吉は朝鮮ではなくその先の中国を目指したのですが、失敗しています。朝鮮という不慣れな土地で戦ったことは、豊臣恩顧の家臣たちを分裂に追いやり、諸国の武将たちを疲弊させただけで終わり、この戦にかかわらなかった徳川家康の力を強めることにもなりました。
そして、それは「関ヶ原の戦い」から「大阪の陣」で豊臣家の滅亡にもつながっていくのです。
秀長が生きていれば防げたかもしれない「関ケ原の戦い」
秀長が生きていれば、秀吉の死後に石田三成と加藤清正らの家臣たちが割れることを防げたかもしれません。秀次切腹や、朝鮮出兵自体なかったかもしれません。秀長には子供がなく、彼の資質を継いだ子供がいれば跡取りの秀頼を支えたかもしれません。秀長の死が、豊臣滅亡の原因の一つになったことは間違いないです。
豊臣秀長の家紋は「五七桐」
 五七桐
五七桐
豊臣秀長の家紋は、秀吉と同じ「五七桐」です。これは秀吉が天皇から下賜された家紋で、豊臣家の象徴でもあります。秀吉は、後に「太閤桐」という家紋を独自に作っていますが、やはり「五七の桐」の方が有名ですよね。桐は高級木材として、菊紋についで天皇家や功績をあげた者の家紋として用いられました。その風習のはじまりは、後鳥羽上皇から足利尊氏が桐紋を賜ったことです。その後、桐紋が広く広まったのは皇室が臣下へ、下賜された武将が臣下へと付与したことによります。桐紋は桐の葉と花を図案化したもので、一般的には3枚の葉の上に3本の花が描かれ、その花の数によって五三桐、五七桐など呼び名が異なります。豊臣秀吉の家紋は太閤桐と呼ばれ、特定の一つの紋ではなく秀吉の遺品などに確認される桐紋のうち、独自のアレンジが入ったものの総称です。秀吉が家臣に与えたので西日本を中心に多く用いられています。
スポンサードリンク
戦国武将117名の家紋一覧をまとめてチェックしよう
 織田木瓜 織田木瓜 |
 大一大万大吉 大一大万大吉 |
 太閤桐 太閤桐 |
 水色桔梗 水色桔梗 |
| 石田三成 | 豊臣秀吉 | 明智光秀/山県昌景 |
|
 竹に二羽飛び雀/上杉笹 竹に二羽飛び雀/上杉笹 |
 武田菱 武田菱 |
 真田六文銭 真田六文銭 |
 竹に雀/仙台笹 竹に雀/仙台笹 |
| 上杉謙信/上杉景勝/伊達成実 | 武田信玄/武田信繁/武田勝頼/安国寺恵瓊 | 真田幸村/真田昌幸 | 伊達政宗 |
 蛇の目 蛇の目 |
 徳川葵 徳川葵 |
 黒田藤巴 黒田藤巴 |
 向い蝶 向い蝶 |
| 加藤清正 | 徳川家康/徳川秀忠 | 黒田官兵衛/黒田長政 | 大谷 吉継 |
 前田梅鉢/剣梅鉢 |
 一文字三星 一文字三星 |
 池田蝶 池田蝶 |
 足利二つ引き 足利二つ引き |
| 前田利家/前田慶次 | 毛利元就/毛利輝元 | 池田恒興/池田輝政 | 今川義元 |
 丸に立ち葵 丸に立ち葵 |
 九枚笹 九枚笹 |
 二頭立波 二頭立波 |
 二つ雁金 二つ雁金 |
| 本多忠勝 | 竹中半兵衛 | 斎藤道三 | 柴田勝家 |
 丸に竪木瓜 丸に竪木瓜 |
 三つ盛木瓜に剣花菱 三つ盛木瓜に剣花菱 |
 福島沢瀉 福島沢瀉 |
 井伊橘 井伊橘 |
| 滝川一益 | 直江兼続 | 福島正則 | 井伊直虎/井伊直政 |
 鶴丸 鶴丸 |
 丸に細桔梗 丸に細桔梗 |
 丸に七つ片喰 丸に七つ片喰 |
 剣片喰 剣片喰 |
| 森蘭丸/森長可 | 太田道灌 | 長宗我部元親 | 宇喜多秀家 |
 土佐柏 土佐柏 |
 三つ柏 三つ柏 |
 八咫烏 八咫烏 |
 平四つ目結 平四つ目結 |
| 山内一豊 | 島左近 | 雑賀孫一 | 尼子晴久/京極高次 |
 ばら藤に井桁 ばら藤に井桁 |
 丸に違い鎌 丸に違い鎌 |
 蔦 蔦 |
 大友抱き花杏葉 大友抱き花杏葉 |
| 片倉小十郎 | 小早川秀秋 | 藤堂高虎/松永久秀 | 大友宗麟/高橋紹運/立花道雪 |
 中結び祇園守 中結び祇園守 |
 祇園守 祇園守 |
 足利二つ引き 足利二つ引き |
 対い鶴 対い鶴 |
| 小西行長 | 立花宗茂 | 足利尊氏/足利義昭 | 蒲生氏郷 |
 七つ割り隅立て四つ目 七つ割り隅立て四つ目 |
 細川九曜 細川九曜 |
 笹龍胆 笹龍胆 |
 丹羽直違 丹羽直違 |
| 佐々成政 | 細川忠興 細川藤孝 |
源頼朝 | 丹羽長秀 |
 丸に片喰 丸に片喰 |
 榊原源氏車 榊原源氏車 |
 三つ盛り木瓜 三つ盛り木瓜 |
 違い鷹の羽 |
| 酒井忠次 | 榊原康政 | 朝倉義景 | 片桐且元 |
 下がり藤 下がり藤 |
 黒餅 黒餅 |
 北条対い蝶 北条対い蝶 |
 丸に二つ引き 丸に二つ引き |
| 加藤嘉明 | 黒田長政 | 北条早雲 | 最上義光 |
 三つ盛り亀甲に花菱 三つ盛り亀甲に花菱 |
 丸に十文字 丸に十文字 |
 蜂須賀卍 蜂須賀卍 |
 七曜 七曜 |
| 浅井長政 | 島津義弘/島津貴久/島津貴久/島津義久 | 蜂須賀 小六(正勝) | 高山右近/九鬼嘉隆 |
 津軽牡丹 津軽牡丹 |
 北条鱗 北条鱗 |
 丸に上の字 丸に上の字 |
 右三つ巴 右三つ巴 |
| 津軽為信 | 北条氏康/北条氏政 | 村上義清/村上武吉 | 結城秀康/清水宗治/山本勘助/小早川隆景 |
 永楽銭 永楽銭 |
 梅鉢 梅鉢 |
 変わり十二日足 変わり十二日足 |
 丸に三つ引き 丸に三つ引き |
| 仙石秀久 | 筒井順慶 | 龍造寺隆信 | 吉川広家 |
 丸に違い鷹の羽 丸に違い鷹の羽 |
 五七桐 五七桐 |
 生駒車 生駒車 |
 九条下がり藤 九条下がり藤 |
| 浅野幸長/浅野長政 | 豊臣秀次/斎藤義龍/豊臣秀長 | 生駒正俊 | 本願寺顕如 |
 丸に揚羽蝶 丸に揚羽蝶 |
 吾亦紅/地楡に雀 吾亦紅/地楡に雀 |
 丸に三つ葵 丸に三つ葵 |
 輪違い 輪違い |
| 平清盛 | 柳生宗矩 | 松平忠吉 | 脇坂安治 |
 鍋島花杏葉 鍋島花杏葉 |
 結城巴 結城巴 |
 揚羽蝶 揚羽蝶 |
 唐花紋 唐花紋 |
| 鍋島勝茂 | 松平忠直 | 吉川元春 | 陶晴賢 |
 抱き茗荷 抱き茗荷 |
 五本骨扇に月丸 五本骨扇に月丸 |
||
| 堀尾吉晴 | 佐竹義重 |
スポンサードリンク
| 他にもあるぞ!超人気家紋コンテンツ |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |