戦国時代において、武将は「1人の主に仕えること」が美徳とされていました。主君が戦で敗走したリ、命を落としたりということがあった場合は家臣も一緒に死ぬということが当たり前とされていたのです。しかし、そんな時代の中で何度も主人を変えた異例の武将が藤堂高虎です。今回はその藤堂高虎がこれまで使えた7人の主君や彼が使った家紋の由来について解説していきます。

スポンサードリンク
目次
|
|
|
なんと7度の主君替え!なぜこのようなことになったのか
藤堂高虎は、生涯の中で以下の複数の主に仕えました。ちなみにそれぞれの代表的な家紋も記載しておきます。
| No | 主君名 | 家紋 | 家紋名 |
| 1 | 浅井長政 | 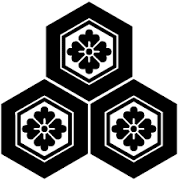 |
三つ盛亀甲 |
| 2 | 阿閉貞征(浅井家家臣) | 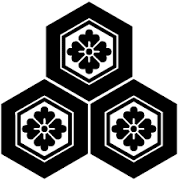 |
三つ盛亀甲 |
| 3 | 磯野員昌(浅井家家臣) | 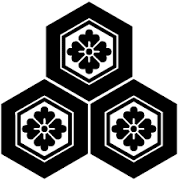 |
三つ盛亀甲 |
| 4 | 津田信澄(信長の甥っ子) | 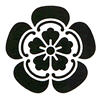 |
織田木瓜 |
| 5 | 豊臣秀長(秀吉の弟)~豊臣秀保(秀長の子) |  |
五七の桐 |
| 6 | 豊臣秀吉 | 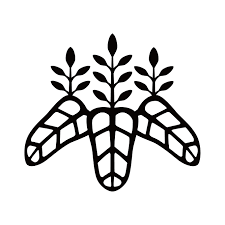 |
太閤紋 |
| 7 | 徳川家康~徳川秀忠(家康の三男) | 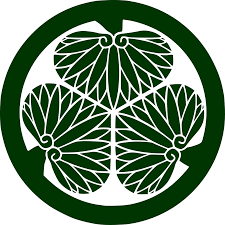 |
三つ葵 |
※阿閉貞征、磯野員昌は浅井家の家臣なので浅井長政の家紋、豊臣秀長は秀吉の弟のため五七桐と想定します。
初代主君の浅井長政~豊臣秀長までを解説
簡単に経緯を振り返ってみましょう。まず、高虎が最初に仕えたのは近江の大名・浅井長政です。しかし、この時に同僚とのもめ事で相手を切り殺してしまったために出奔を余儀なくされ、長政の部下であった阿閉貞征に仕えるようになりました。ここも彼には合わなかったようで、一か月ほどでやはり出奔しています。その後、彼はやはり浅井家にゆかりのある磯野員昌のところに仕えますが、ここも長き続きしていません。津田信澄に仕えたときは、せっかく功績をあげたのに石高を増やしてもらえなかったために出て行ってしまいました。
秀吉の弟、羽柴秀長と相性があった高虎

それから、高虎が向かったのは羽柴秀吉(のちの豊臣秀吉)の弟にあたる羽柴秀長のところです。この秀長と高虎は相性が良かったようで、高虎は功績をあげては石高を与えられとても大切にされました。余談ですが、高虎の家は武家であったものの貧しく、農民とほぼ変わらない生活をしていたそうです。秀吉の一族ももとは農民でしたので、もしかするとこのあたりで感じ合うところがあったのかもしれません。
家康との運命的な出会いをする藤堂高虎
ここで、高虎は後につながる運命的な出会いをします。関白になった秀吉に会うために徳川家康が上洛することになったのですが、秀吉は自分の邸内に家康のための屋敷を造ることを思いつきます。
スポンサードリンク
身銭で家康のために作った屋敷に家康が感動

そこで、作事奉行に選ばれたのが藤堂高虎でした。高虎は渡された設計図通りではなく、自分のお金を使ってより警備に優れた屋敷を作り上げました。このことに、家康は非常に感謝したと言います。これが高虎と家康の出会いです。その後、主であった秀長が亡くなり、さらにその子供であった秀保も若くして亡くなりました。高虎は2人の主を弔うために出家しますが、その能力の高さを評価していた秀吉が呼び戻しています。その後、秀吉のもとで伊予の大名として活躍。この時、宇和島城のあるじとなっています。
引用:https://ja.wikipedia.org/
秀吉没後ついに徳川家へに使える高虎
秀吉が亡くなった後、時代は徳川へと流れていきます。この流れをいち早く汲み取った高虎は、徳川家康につくことを決意。以前に秀吉の命令で家康の屋敷を作った経験が、ここで活かされるわけです。高虎が任されていたのは「諜報」だったので、家康からかなり信頼されていたこともわかるでしょう。実際、高虎からもたらされる情報で家康は命を救われています。関ヶ原の戦いでは、豊臣側の家臣であった時代が長いにも関わらず徳川に加勢し、朽木元綱をはじめとする武将たちの裏切りを事前工作しています。
家康没後には日光東照宮の造営を担当

家康はよほど高虎を気に入っていたのか、高虎が外様大名であるにも関わらず江戸に近い場所に呼ばれ、家康のために尽力しています。家康が亡くなったあとは、日光東照宮の造営も担当。そして家康が「高虎と天海と一緒に眠れるようにしてほしい」と言った遺言通り、日光東照宮には高虎の魂も祀られています。
あまりいいようには語られない高虎、しかし優れた才能を持つ人物だった
戦国時代の武将は、1人に仕えることが美徳とされてきました。その中で、実に7度も主君を変えている高虎の評価は決していいものではありません。「義理がない」「裏切り者」「信用ならない」など言われようは散々です。しかし、高虎は自分が仕えている間は一生懸命主君に仕えていますし、「人をなかなか信用しない」という家康にも気に入られていることから、世間で語られるような人物ではないのでは、という評価もあります。
スポンサードリンク
武ではなく設計士として才能を発揮する高虎
また、彼は戦国の世の中で大変に優れた設計士でした。高虎は決して武に秀でた人物ではなかったため、独自で勉強をして建築の知識を得ていたのです。彼が築いた宇和島城は海に面しており、さらに海水を利用して作った堀があるために敵が攻め込むのは大変です。このように、地形を最大限に生かして防御力の高い城を築いたことは、後世にも高く評価されています。ちなみに、「板島」と呼ばれていたこの島を「宇和島」という名称に変えたのも高虎です。
藤堂高虎の家紋は「蔦紋」

藤堂高虎が使用していた家紋は「蔦紋」。蔦(ツタ)とは、壁などに張り付いているあのツタのことです。ツタは絡みついて茎をのばすことから「生命力が強い植物」と言われてきました、このため、縁起がいいとして家紋に多く使用されています。高虎が使用していた紋は、その中でも「藤堂蔦」と命名され、他のものとは区別されています。
スポンサードリンク
「自分が嫌になったら出て行ってもいい」という考えだった高虎

戦国時代の「武将は一人の主君に尽くすべき」という考え方とは違い、実に七度も主君を変えている高虎。そんな高虎だからこそ、彼は「自分が嫌になった出て行ってもいい。他の誰かに仕えてもいい。そして、そこが合わなければ戻ってきなさい。元のように扱う」と家臣たちに言っていました。彼の生き方そのものの教えですね。裏切り者と言われることもある高虎ですが、時世を見て行動できる優れた武将であったと言い換えることもできます。また、彼は身長が190センチという巨漢でありながら、度重なる戦で体中に傷があったことも解っています。周りに何と言われようが、彼は彼の義をもって戦国時代を生きたのではないでしょうか。
スポンサードリンク
戦国武将117名の家紋一覧をまとめてチェックしよう
 織田木瓜 織田木瓜 |
 大一大万大吉 大一大万大吉 |
 太閤桐 太閤桐 |
 水色桔梗 水色桔梗 |
| 石田三成 | 豊臣秀吉 | 明智光秀/山県昌景 |
|
 竹に二羽飛び雀/上杉笹 竹に二羽飛び雀/上杉笹 |
 武田菱 武田菱 |
 真田六文銭 真田六文銭 |
 竹に雀/仙台笹 竹に雀/仙台笹 |
| 上杉謙信/上杉景勝/伊達成実 | 武田信玄/武田信繁/武田勝頼/安国寺恵瓊 | 真田幸村/真田昌幸 | 伊達政宗 |
 蛇の目 蛇の目 |
 徳川葵 徳川葵 |
 黒田藤巴 黒田藤巴 |
 向い蝶 向い蝶 |
| 加藤清正 | 徳川家康/徳川秀忠 | 黒田官兵衛/黒田長政 | 大谷 吉継 |
 前田梅鉢/剣梅鉢 |
 一文字三星 一文字三星 |
 池田蝶 池田蝶 |
 足利二つ引き 足利二つ引き |
| 前田利家/前田慶次 | 毛利元就/毛利輝元 | 池田恒興/池田輝政 | 今川義元 |
 丸に立ち葵 丸に立ち葵 |
 九枚笹 九枚笹 |
 二頭立波 二頭立波 |
 二つ雁金 二つ雁金 |
| 本多忠勝 | 竹中半兵衛 | 斎藤道三 | 柴田勝家 |
 丸に竪木瓜 丸に竪木瓜 |
 三つ盛木瓜に剣花菱 三つ盛木瓜に剣花菱 |
 福島沢瀉 福島沢瀉 |
 井伊橘 井伊橘 |
| 滝川一益 | 直江兼続 | 福島正則 | 井伊直虎/井伊直政 |
 鶴丸 鶴丸 |
 丸に細桔梗 丸に細桔梗 |
 丸に七つ片喰 丸に七つ片喰 |
 剣片喰 剣片喰 |
| 森蘭丸/森長可 | 太田道灌 | 長宗我部元親 | 宇喜多秀家 |
 土佐柏 土佐柏 |
 三つ柏 三つ柏 |
 八咫烏 八咫烏 |
 平四つ目結 平四つ目結 |
| 山内一豊 | 島左近 | 雑賀孫一 | 尼子晴久/京極高次 |
 ばら藤に井桁 ばら藤に井桁 |
 丸に違い鎌 丸に違い鎌 |
 蔦 蔦 |
 大友抱き花杏葉 大友抱き花杏葉 |
| 片倉小十郎 | 小早川秀秋 | 藤堂高虎/松永久秀 | 大友宗麟/高橋紹運/立花道雪 |
 中結び祇園守 中結び祇園守 |
 祇園守 祇園守 |
 足利二つ引き 足利二つ引き |
 対い鶴 対い鶴 |
| 小西行長 | 立花宗茂 | 足利尊氏/足利義昭 | 蒲生氏郷 |
 七つ割り隅立て四つ目 七つ割り隅立て四つ目 |
 細川九曜 細川九曜 |
 笹龍胆 笹龍胆 |
 丹羽直違 丹羽直違 |
| 佐々成政 | 細川忠興 細川藤孝 |
源頼朝 | 丹羽長秀 |
 丸に片喰 丸に片喰 |
 榊原源氏車 榊原源氏車 |
 三つ盛り木瓜 三つ盛り木瓜 |
 違い鷹の羽 |
| 酒井忠次 | 榊原康政 | 朝倉義景 | 片桐且元 |
 下がり藤 下がり藤 |
 黒餅 黒餅 |
 北条対い蝶 北条対い蝶 |
 丸に二つ引き 丸に二つ引き |
| 加藤嘉明 | 黒田長政 | 北条早雲 | 最上義光 |
 三つ盛り亀甲に花菱 三つ盛り亀甲に花菱 |
 丸に十文字 丸に十文字 |
 蜂須賀卍 蜂須賀卍 |
 七曜 七曜 |
| 浅井長政 | 島津義弘/島津貴久/島津貴久/島津義久 | 蜂須賀 小六(正勝) | 高山右近/九鬼嘉隆 |
 津軽牡丹 津軽牡丹 |
 北条鱗 北条鱗 |
 丸に上の字 丸に上の字 |
 右三つ巴 右三つ巴 |
| 津軽為信 | 北条氏康/北条氏政 | 村上義清/村上武吉 | 結城秀康/清水宗治/山本勘助/小早川隆景 |
 永楽銭 永楽銭 |
 梅鉢 梅鉢 |
 変わり十二日足 変わり十二日足 |
 丸に三つ引き 丸に三つ引き |
| 仙石秀久 | 筒井順慶 | 龍造寺隆信 | 吉川広家 |
 丸に違い鷹の羽 丸に違い鷹の羽 |
 五七桐 五七桐 |
 生駒車 生駒車 |
 九条下がり藤 九条下がり藤 |
| 浅野幸長/浅野長政 | 豊臣秀次/斎藤義龍/豊臣秀長 | 生駒正俊 | 本願寺顕如 |
 丸に揚羽蝶 丸に揚羽蝶 |
 吾亦紅/地楡に雀 吾亦紅/地楡に雀 |
 丸に三つ葵 丸に三つ葵 |
 輪違い 輪違い |
| 平清盛 | 柳生宗矩 | 松平忠吉 | 脇坂安治 |
 鍋島花杏葉 鍋島花杏葉 |
 結城巴 結城巴 |
 揚羽蝶 揚羽蝶 |
 唐花紋 唐花紋 |
| 鍋島勝茂 | 松平忠直 | 吉川元春 | 陶晴賢 |
 抱き茗荷 抱き茗荷 |
 五本骨扇に月丸 五本骨扇に月丸 |
||
| 堀尾吉晴 | 佐竹義重 |
スポンサードリンク
| 他にもあるぞ!超人気家紋コンテンツ |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |


