織田信長の小姓として有名な森蘭丸。その蘭丸の兄にあたるのが「森長可」です。「もり ながよし」と読みます。有名すぎる蘭丸と比べると、知名度が低めの森長可ですが、個性派揃いの信長の家臣だけあって、彼もまた面白い逸話を遺しています。
スポンサードリンク
目次
|
|
|
信長にめちゃくちゃ可愛がられた森長可・その破天荒な人柄に迫る
森長可は、信長の家臣・森可成(よしなり)の次男として生まれました。次男なので、当初は家督相続をせず長男が森家を継いでいたのですが、父・兄が相次いで戦で亡くなってしまったため、森家の当主となりました。
長可の「長は」信長からもらったもの
父が優秀な家臣であったことから、信長は遺された子供たちのことを大層可愛がります。弟の蘭丸は信長の小姓となり、長可は織田家の嫡男・織田信忠に仕えるなど、破格の扱いを受けました。
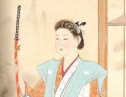 森成利の家紋とは?森蘭丸(乱丸)と呼ばれた信長の小姓で本能寺の変で命を落とした戦国武将
森成利の家紋とは?森蘭丸(乱丸)と呼ばれた信長の小姓で本能寺の変で命を落とした戦国武将
スポンサードリンク
弟の蘭丸はインテリに対して長可はやんちゃ
弟の森蘭丸は大層頭が良く、その優秀さを信長が買っていたのは有名ですが、この長可はとにかく「やんちゃ」。どのくらいやんちゃなのかというと、関所で止められれば止めた人間を切り殺し、橋を通ろうとしたときに止められれば相手を殺す、という逸話が残るくらいです。。信長も信長で、「橋の上で人を斬るのは武蔵坊弁慶を思わせる。武蔵守と名乗ればいい」というわけのわからない言葉だけで済ませたそうなので、やっぱりお気に入りだったのでしょうね。このやんちゃさに比例するように、戦も巧くて戦果もよく挙げていたようです。ただ、甘やかされたせいかもともとの資質か、軍のルールを守らずに勝手に行動することも多かったので、さすがに信長も怒ったといいます。この長可は信長と蘭丸が「本能寺の変」で討ち死したあとも生き続けました。
信長亡き後は秀吉につく~しかし27歳で討ち死
信長が亡くなったのち、織田家では当主争いが勃発。信長の次男・信雄を推す羽柴秀吉と、三男・信孝を推す柴田勝家が対立してしまいます。当主を決めるために「清須会議」では、信忠の嫡男・三法師を当主にすることが決まったものの、両者の溝は埋まりませんでした。
賤ケ岳の戦いで敗れる柴田勝家
秀吉は「賤ヶ岳の戦い」で柴田勝家・織田信孝を自害に追い込み勝利します。しかし、もはや織田家をしのぐほどの力を得た秀吉は、残された信雄を必要としていませんでした。
小牧長久手の戦いで秀吉軍に就く長可
信雄は、徳川家康と共に秀吉を討つべく挙兵し、秀吉も戦うことを決意(「小牧長久手の戦い」)。長可は秀吉軍に加わって戦いますが、戦はなかなか決着がつかない状態でした。事態を動かすために、秀吉の甥・豊臣秀次が総大将になって軍を率いますが、この軍の第2軍を率いたのが長可です。死を覚悟していた長可は、鎧の上から白装束を着て戦に挑み、敵軍の将を討ち取るなど大きな活躍を見せます。しかし、徳川家康軍の井伊直政軍と戦っているときに眉間を討たれ、27歳でこの世を去りました。
長可が遺した遺書から見える、また別の人柄
長可自身が持つエピソードや、戦上手という評判から「猛将」という印象ばかりが強いですが、一方で書を愛し、戦にも紙や筆を持ち込んでいたそうです。何か報告しなければならないことがあると、自分で筆をとって書を書いたとか。それもあって、長可は「小牧長久手の戦い」の中で妻にあてた遺書をしたため、自分が死んだあとの森家について指示もしています。
スポンサードリンク
遺書には子供にはお医者さんを勧める
この遺書の中に幼い子供たちについて書かれているのですが、娘については「武士の妻ではなく、庶民の嫁になってほしい。できればお医者さんがいい」と書き遺しています。父と兄を早くに亡くし、その後は可愛がってくれた信長と弟の蘭丸を亡くし…「猛将」として勇ましいエピソードを遺しながらも、子供たちには自分と同じような目にあってほしくなかったのでしょう。この遺言状は内容が「異様」ともいえるものだったため、秀吉も扱いに困ったそうなのですが、自分亡き後の家のことを慮る長可の心が透けて見えます。ただ、さすがに武家の娘が庶民の嫁に…というのは考えられないことで、遺言は守られることなく娘は武家に嫁ぎました。
森長可の家紋とは
 鶴丸
鶴丸
森長可が使用していた家紋は「鶴丸」です。鶴が二つの羽を広げたような、とても鮮やかな家紋ですね。
「鶴」は長寿の動物であること、姿も鳴き声も美しいことから、家紋に使用されるようになりました。森家では、この鶴丸の家紋を代々使っていたようですね。
鶴丸紋の逸話
この「鶴丸紋」ですが、有名な逸話があります。日本航空が、フランスの著名なアーティストに「会社のロゴを作ってもらえないか」と頼んだところ、「日本の伝統をみなさい。素晴らしいものがあるではありませんか」と言われました。そこで、鶴丸の家紋に似たデザインのロゴを作り上げたのです。日本の奥ゆかしい伝統が産みだした、とても美しい家紋ですね。
スポンサードリンク
戦国武将117名の家紋一覧をまとめてチェックしよう
 織田木瓜 織田木瓜 |
 大一大万大吉 大一大万大吉 |
 太閤桐 太閤桐 |
 水色桔梗 水色桔梗 |
| 石田三成 | 豊臣秀吉 | 明智光秀/山県昌景 |
|
 竹に二羽飛び雀/上杉笹 竹に二羽飛び雀/上杉笹 |
 武田菱 武田菱 |
 真田六文銭 真田六文銭 |
 竹に雀/仙台笹 竹に雀/仙台笹 |
| 上杉謙信/上杉景勝/伊達成実 | 武田信玄/武田信繁/武田勝頼/安国寺恵瓊 | 真田幸村/真田昌幸 | 伊達政宗 |
 蛇の目 蛇の目 |
 徳川葵 徳川葵 |
 黒田藤巴 黒田藤巴 |
 向い蝶 向い蝶 |
| 加藤清正 | 徳川家康/徳川秀忠 | 黒田官兵衛/黒田長政 | 大谷 吉継 |
 前田梅鉢/剣梅鉢 |
 一文字三星 一文字三星 |
 池田蝶 池田蝶 |
 足利二つ引き 足利二つ引き |
| 前田利家/前田慶次 | 毛利元就/毛利輝元 | 池田恒興/池田輝政 | 今川義元 |
 丸に立ち葵 丸に立ち葵 |
 九枚笹 九枚笹 |
 二頭立波 二頭立波 |
 二つ雁金 二つ雁金 |
| 本多忠勝 | 竹中半兵衛 | 斎藤道三 | 柴田勝家 |
 丸に竪木瓜 丸に竪木瓜 |
 三つ盛木瓜に剣花菱 三つ盛木瓜に剣花菱 |
 福島沢瀉 福島沢瀉 |
 井伊橘 井伊橘 |
| 滝川一益 | 直江兼続 | 福島正則 | 井伊直虎/井伊直政 |
 鶴丸 鶴丸 |
 丸に細桔梗 丸に細桔梗 |
 丸に七つ片喰 丸に七つ片喰 |
 剣片喰 剣片喰 |
| 森蘭丸/森長可 | 太田道灌 | 長宗我部元親 | 宇喜多秀家 |
 土佐柏 土佐柏 |
 三つ柏 三つ柏 |
 八咫烏 八咫烏 |
 平四つ目結 平四つ目結 |
| 山内一豊 | 島左近 | 雑賀孫一 | 尼子晴久/京極高次 |
 ばら藤に井桁 ばら藤に井桁 |
 丸に違い鎌 丸に違い鎌 |
 蔦 蔦 |
 大友抱き花杏葉 大友抱き花杏葉 |
| 片倉小十郎 | 小早川秀秋 | 藤堂高虎/松永久秀 | 大友宗麟/高橋紹運/立花道雪 |
 中結び祇園守 中結び祇園守 |
 祇園守 祇園守 |
 足利二つ引き 足利二つ引き |
 対い鶴 対い鶴 |
| 小西行長 | 立花宗茂 | 足利尊氏/足利義昭 | 蒲生氏郷 |
 七つ割り隅立て四つ目 七つ割り隅立て四つ目 |
 細川九曜 細川九曜 |
 笹龍胆 笹龍胆 |
 丹羽直違 丹羽直違 |
| 佐々成政 | 細川忠興 細川藤孝 |
源頼朝 | 丹羽長秀 |
 丸に片喰 丸に片喰 |
 榊原源氏車 榊原源氏車 |
 三つ盛り木瓜 三つ盛り木瓜 |
 違い鷹の羽 |
| 酒井忠次 | 榊原康政 | 朝倉義景 | 片桐且元 |
 下がり藤 下がり藤 |
 黒餅 黒餅 |
 北条対い蝶 北条対い蝶 |
 丸に二つ引き 丸に二つ引き |
| 加藤嘉明 | 黒田長政 | 北条早雲 | 最上義光 |
 三つ盛り亀甲に花菱 三つ盛り亀甲に花菱 |
 丸に十文字 丸に十文字 |
 蜂須賀卍 蜂須賀卍 |
 七曜 七曜 |
| 浅井長政 | 島津義弘/島津貴久/島津貴久/島津義久 | 蜂須賀 小六(正勝) | 高山右近/九鬼嘉隆 |
 津軽牡丹 津軽牡丹 |
 北条鱗 北条鱗 |
 丸に上の字 丸に上の字 |
 右三つ巴 右三つ巴 |
| 津軽為信 | 北条氏康/北条氏政 | 村上義清/村上武吉 | 結城秀康/清水宗治/山本勘助/小早川隆景 |
 永楽銭 永楽銭 |
 梅鉢 梅鉢 |
 変わり十二日足 変わり十二日足 |
 丸に三つ引き 丸に三つ引き |
| 仙石秀久 | 筒井順慶 | 龍造寺隆信 | 吉川広家 |
 丸に違い鷹の羽 丸に違い鷹の羽 |
 五七桐 五七桐 |
 生駒車 生駒車 |
 九条下がり藤 九条下がり藤 |
| 浅野幸長/浅野長政 | 豊臣秀次/斎藤義龍/豊臣秀長 | 生駒正俊 | 本願寺顕如 |
 丸に揚羽蝶 丸に揚羽蝶 |
 吾亦紅/地楡に雀 吾亦紅/地楡に雀 |
 丸に三つ葵 丸に三つ葵 |
 輪違い 輪違い |
| 平清盛 | 柳生宗矩 | 松平忠吉 | 脇坂安治 |
 鍋島花杏葉 鍋島花杏葉 |
 結城巴 結城巴 |
 揚羽蝶 揚羽蝶 |
 唐花紋 唐花紋 |
| 鍋島勝茂 | 松平忠直 | 吉川元春 | 陶晴賢 |
 抱き茗荷 抱き茗荷 |
 五本骨扇に月丸 五本骨扇に月丸 |
||
| 堀尾吉晴 | 佐竹義重 |
スポンサードリンク
| 他にもあるぞ!超人気家紋コンテンツ |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |


