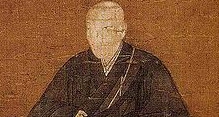京都の観光名所としても知られる「西本願寺」「東本願寺」。特に、「西本願寺」の方は幕末に京都で活躍した「新選組」の屯所として使用されていたことでも有名です。※ただし、屯所として使われていた場所は現在は移築されています。織田信長と対立した本願寺顕如の生涯を家紋とともに解説します。
スポンサードリンク
目次
|
|
|
信長との戦いから「東」「西」に分かれた本願寺!中心となった「本願寺顕如」に迫る
今では、二つの本願寺が分かれていることが当たり前のようになっていますが、もともとはひとつのお寺だったことをご存知ですか?そう、西本願寺も東本願寺も同じ浄土真宗なので、ひとつのお寺にすることも可能だったのです。もともとはひとつのお寺だった「本願寺」が二つに分かれた理由には、織田信長と本願寺顕如という人物が関わっています。
スポンサードリンク
「宗教」が持つ力をおさらいしよう
この「本願寺」というのは、浄土真宗の総本山です。厳密に言うと、今と昔の浄土真宗では違いも大きいのですが、それはここでは割愛します。当時、宗教というのは非常に力を持つものでした。考えてみてください、その宗教を信仰する人が多ければ、そのお寺にはお布施(つまりお金)が集まるようになるでしょう。また、そのお寺で教えを説く法主を人々は尊敬することになります。浄土真宗はたくさんの人が進行している宗教ですから、その総本山である本願寺はかなりの力を持っていました。これを覚えておいてください。この「信仰」という形が、本願寺と織田信長の戦いに深く影響しています。
京都を支配した織田信長が、「第六天魔王」と呼ばれるようになった理由
室町時代に京都で「将軍」だった足利家。その足利家の13代目将軍・足利義輝が、突然暗殺されてしまいます。これにより足利家は将軍職を追われてしまうのですが、義輝の弟・義昭は「もう一度将軍職に返り咲く」という覚悟を決め、兄を暗殺した勢力と戦う人物を探していました。
スポンサードリンク
足利義昭が信頼した人物こそ織田信長
そこで、義昭が頼ったのが織田信長です。信長は義昭と共に上洛(京都へ行くこと)し、無事に義昭を将軍職へと復帰させています。時の将軍を支えた信長ですから、もちろん将軍のいる京都で絶大な力を持つようになります。
信長に挨拶をする願寺顕如
その信長に、当時の本願寺法主・本願寺顕如は自ら出向いて挨拶をします。そう!この時点で本願寺はまだ二つに分かれていません。信長は、その場で顕如に大金を出すように命じますが、顕如はこれにもすぐ応えました。時の権力者だった信長と、なんとかしてうまくやろうとしていたのでしょう。
どんどん信長の要求は過激になっていく
ところが、信長と本願寺側の考え方には違いがあったようです。顕如としては、「本願寺と信長はあくまで対等な関係」と考えていたようですが、信長の方は「本願寺は自分の言うことを聞くべき」という考えだったようで、本願寺が何かする時は必ず織田家に知らせて許可を得るように、と命じます。
スポンサードリンク
織田信長VS本願寺顕如
前述した通り、浄土真宗の総本山である本願寺はそれなりに地位がある存在でした。なのに、織田家の家臣のように扱われることに顕如は強い不快感を抱いていました。さらに、信長が力を得るきっかけとなった将軍・義昭が、信長との関係が悪化して本願寺に助けを求めてきたのです。これにより、顕如は「織田信長と戦う」と決意。全国の門徒に「信長を討つべし」という指令を出しました。
浄土真宗の門徒を次々と惨殺…「第六天魔王」の誕生
もちろん、これで黙る信長ではありません。信長は本願寺と戦い、女性や子供を含めた20000人を殺したり、門徒と解ったらすぐに殺害させたり、稀に見る残虐さを見せています。これにより亡くなった門徒は、70000人に上るとも言われています。信長は、戦いで滅ぼした浅井家・朝倉家の人間をかくまった比叡山・延暦寺でも3000人の僧を殺害しており、そのことに恐怖を抱いた人々が「第六天魔王」と呼ぶようになりました。
本願寺では2000人、延暦寺では3000人を殺害する信長
とはいえ、信長がここまでの行動に出たことの背景には「宗教」というものの強さがあります。ここで門徒たちの命を助けたとしても、信長に従うことはありません、門徒というのは何があっても信仰をとるもの。つまり、本願寺の力を削ぐためには門徒を殺して、信仰する人間を力づくで減らすしかなかったのです。また、家臣や親族でさえ主にとって代わろうとする戦国の世で、徹底的におのれの怖さを見せつけなければ自分が食われる、という危機感もあったでしょう。織田信長がやったことは確かに残虐極まりないのですが、それにも理由があるということを明記しておきます。敵には厳しい信長ですが、民衆には優しかったという話しも伝わっています。本願寺の門徒との戦いの中で、信長も兄と弟を含めた身内を多数失いました。そのことも、信長の心にあったのかもしれませんね。
スポンサードリンク
10年にわたる信長との戦いに終止符~しかし本願寺が分裂してしまう事態に
信長と本願寺の戦いは、実に10年にも及びました。信長の恐ろしさの前に、各地の門徒たちも次第におとなしくなり、顕如もとうとう降伏。命は助けられましたが、本願寺は出ることになりました。しかし、顕如の息子であった教如はそれを良しとせず、徹底抗戦を唱え本願寺に居座ります。
顕如率いる「西本願寺」と教如率いる「東本願寺」に分裂
これで親子は決裂。本願寺は顕如率いる「西本願寺」と教如率いる「東本願寺」に分かれたのです。そしてそのまま、二つのお寺は今も京都にて人々を見守り続けています。
本願寺顕如の家紋「下り藤」を解説
本願寺顕如が使用していた家紋は「下り藤」です。

本願寺は「西本願寺」「東本願寺」以外にも各地にありますが、そのすべてがこの下がり藤を使っているわけではないようです。でも、本願寺と言ったらやはりこの家紋のイメージが強いですよね。
藤はマメ科のつる性落葉木本で、淡い紫色の花を咲かせ華やかな藤棚を作ります。古くから観賞用の花として親しまれ、繁殖力の強さから、めでだいとされる縁起の良い植物です。藤原氏が藤紋を用いたことで武家や庶民の家紋にも使用され、江戸時代には幕臣約160の家紋となったほど代表的な家紋です。石田三成や大久保利通も藤紋を使用していました。使用者は、公家では一条家、二条家、九条家、武家では本願寺氏、大久保氏、片倉氏、黒田氏、新庄氏です。また、「藤」の付く名字にちなんで安藤氏、加藤氏、内藤氏、藤井氏、佐藤氏なども使用しています。特に藤の葉を左右に伸ばし円型に描く藤丸や、十字形の八つ藤が人気となっていました。
スポンサードリンク
戦国武将117名の家紋一覧をまとめてチェックしよう
 織田木瓜 織田木瓜 |
 大一大万大吉 大一大万大吉 |
 太閤桐 太閤桐 |
 水色桔梗 水色桔梗 |
| 石田三成 | 豊臣秀吉 | 明智光秀/山県昌景 |
|
 竹に二羽飛び雀/上杉笹 竹に二羽飛び雀/上杉笹 |
 武田菱 武田菱 |
 真田六文銭 真田六文銭 |
 竹に雀/仙台笹 竹に雀/仙台笹 |
| 上杉謙信/上杉景勝/伊達成実 | 武田信玄/武田信繁/武田勝頼/安国寺恵瓊 | 真田幸村/真田昌幸 | 伊達政宗 |
 蛇の目 蛇の目 |
 徳川葵 徳川葵 |
 黒田藤巴 黒田藤巴 |
 向い蝶 向い蝶 |
| 加藤清正 | 徳川家康/徳川秀忠 | 黒田官兵衛/黒田長政 | 大谷 吉継 |
 前田梅鉢/剣梅鉢 |
 一文字三星 一文字三星 |
 池田蝶 池田蝶 |
 足利二つ引き 足利二つ引き |
| 前田利家/前田慶次 | 毛利元就/毛利輝元 | 池田恒興/池田輝政 | 今川義元 |
 丸に立ち葵 丸に立ち葵 |
 九枚笹 九枚笹 |
 二頭立波 二頭立波 |
 二つ雁金 二つ雁金 |
| 本多忠勝 | 竹中半兵衛 | 斎藤道三 | 柴田勝家 |
 丸に竪木瓜 丸に竪木瓜 |
 三つ盛木瓜に剣花菱 三つ盛木瓜に剣花菱 |
 福島沢瀉 福島沢瀉 |
 井伊橘 井伊橘 |
| 滝川一益 | 直江兼続 | 福島正則 | 井伊直虎/井伊直政 |
 鶴丸 鶴丸 |
 丸に細桔梗 丸に細桔梗 |
 丸に七つ片喰 丸に七つ片喰 |
 剣片喰 剣片喰 |
| 森蘭丸/森長可 | 太田道灌 | 長宗我部元親 | 宇喜多秀家 |
 土佐柏 土佐柏 |
 三つ柏 三つ柏 |
 八咫烏 八咫烏 |
 平四つ目結 平四つ目結 |
| 山内一豊 | 島左近 | 雑賀孫一 | 尼子晴久/京極高次 |
 ばら藤に井桁 ばら藤に井桁 |
 丸に違い鎌 丸に違い鎌 |
 蔦 蔦 |
 大友抱き花杏葉 大友抱き花杏葉 |
| 片倉小十郎 | 小早川秀秋 | 藤堂高虎/松永久秀 | 大友宗麟/高橋紹運/立花道雪 |
 中結び祇園守 中結び祇園守 |
 祇園守 祇園守 |
 足利二つ引き 足利二つ引き |
 対い鶴 対い鶴 |
| 小西行長 | 立花宗茂 | 足利尊氏/足利義昭 | 蒲生氏郷 |
 七つ割り隅立て四つ目 七つ割り隅立て四つ目 |
 細川九曜 細川九曜 |
 笹龍胆 笹龍胆 |
 丹羽直違 丹羽直違 |
| 佐々成政 | 細川忠興 細川藤孝 |
源頼朝 | 丹羽長秀 |
 丸に片喰 丸に片喰 |
 榊原源氏車 榊原源氏車 |
 三つ盛り木瓜 三つ盛り木瓜 |
 違い鷹の羽 |
| 酒井忠次 | 榊原康政 | 朝倉義景 | 片桐且元 |
 下がり藤 下がり藤 |
 黒餅 黒餅 |
 北条対い蝶 北条対い蝶 |
 丸に二つ引き 丸に二つ引き |
| 加藤嘉明 | 黒田長政 | 北条早雲 | 最上義光 |
 三つ盛り亀甲に花菱 三つ盛り亀甲に花菱 |
 丸に十文字 丸に十文字 |
 蜂須賀卍 蜂須賀卍 |
 七曜 七曜 |
| 浅井長政 | 島津義弘/島津貴久/島津貴久/島津義久 | 蜂須賀 小六(正勝) | 高山右近/九鬼嘉隆 |
 津軽牡丹 津軽牡丹 |
 北条鱗 北条鱗 |
 丸に上の字 丸に上の字 |
 右三つ巴 右三つ巴 |
| 津軽為信 | 北条氏康/北条氏政 | 村上義清/村上武吉 | 結城秀康/清水宗治/山本勘助/小早川隆景 |
 永楽銭 永楽銭 |
 梅鉢 梅鉢 |
 変わり十二日足 変わり十二日足 |
 丸に三つ引き 丸に三つ引き |
| 仙石秀久 | 筒井順慶 | 龍造寺隆信 | 吉川広家 |
 丸に違い鷹の羽 丸に違い鷹の羽 |
 五七桐 五七桐 |
 生駒車 生駒車 |
 九条下がり藤 九条下がり藤 |
| 浅野幸長/浅野長政 | 豊臣秀次/斎藤義龍/豊臣秀長 | 生駒正俊 | 本願寺顕如 |
 丸に揚羽蝶 丸に揚羽蝶 |
 吾亦紅/地楡に雀 吾亦紅/地楡に雀 |
 丸に三つ葵 丸に三つ葵 |
 輪違い 輪違い |
| 平清盛 | 柳生宗矩 | 松平忠吉 | 脇坂安治 |
 鍋島花杏葉 鍋島花杏葉 |
 結城巴 結城巴 |
 揚羽蝶 揚羽蝶 |
 唐花紋 唐花紋 |
| 鍋島勝茂 | 松平忠直 | 吉川元春 | 陶晴賢 |
 抱き茗荷 抱き茗荷 |
 五本骨扇に月丸 五本骨扇に月丸 |
||
| 堀尾吉晴 | 佐竹義重 |
スポンサードリンク
| 他にもあるぞ!超人気家紋コンテンツ |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |