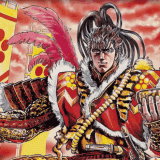織田信雄は、織田信長の次男に当たる人物です。織田信長という偉大な父を持ちながら、数奇な運命をたどることになった織田信雄。実は世界遺産に認定された「富岡製糸場」にもつながりがある信雄の生涯をみていきましょう。父・信長に比べるとずっと地味ですが、面白い運命をたどった人です。
スポンサードリンク
目次
|
|
|
三男・織田信孝との因縁

織田信長には、たくさんの子供がいたことが解っています。その中で、信長が家督を譲ったのは長男の織田信忠。織田信雄はその下の次男に生まれた人物です…が、実は諸説あり、三男の織田信孝の方が先に生まれていたという説があります。しかし信孝の母は身分が低かったため、信雄の方が先に生まれたことにしたとか。生まれた時からこのような事情があった信雄と信孝なのですが、この因縁が今後に大きく関わってきます…。
スポンサードリンク
信雄の運命が大きく変わった「本能寺の変」
信長が信忠に家督を譲り、織田家は安泰かに思われました。ところが、あの「本能寺の変」が信雄の運命を大きく変えてしまいます。「本能寺の変」で信長が死に、そして家督を継いだ信忠も明智光秀軍と闘い命を落としました。※ちなみに、信忠は信長と別の場所にいたので逃げれば助かったのですが、彼は御所に向かって天皇家の人たちを逃がした上で明智軍と戦っています。さすが信長の子。
信雄より早く動いた秀吉による「中国大返し」
この話を聞き、信雄ももちろん明智光秀を討とうとしますが、その前に「中国大返し」をして戻ってきた羽柴秀吉が信長の仇を討ちました。近年では否定されているのですが、信雄は明智軍が去った安土城と城下町に火をつけ、焼失させてしまったという説があります。安土城はもともと信長のものでしたし、信雄が火をつける理由は一切ないので「織田信雄は無能」と言われる要因になってしまったとか…。今も信雄には「無能」の評価が付きまとうので、これが事実でないなら大きな誤解ですね。
清須会議で対立した次男の信雄と三男の信孝
この後、信長と信忠を失った織田家では「清州会議」が開かれ、跡取りを決めることになります。「清須会議」は、織田家の筆頭家老として力を持っていた柴田勝家が招集したもの。勝家も信長の仇を討ちたいと考えたものの、当時は北の上杉景勝と戦っていたため向かうことはできませんでした。その中で、敵を討ったのは羽柴秀吉。まあ、この二人が仲良くできるわけがありません。この時点で信雄と信孝は「どちらが当主になるか」ですでに揉めていたと言います。二人とも会議への出席を許されなかったくらいですから、顔を合わせたら必ず喧嘩になると周囲からも思われていたのでしょう。
スポンサードリンク
柴田勝家と秀吉で別れた信長の後継者
信長の子供二人が不在の中で行われた清須会議では、
・柴田勝家→三男の織田信孝
・羽柴秀吉→次男の織田信雄
をそれぞれ当主にしたいと主張し、対立します。※「清須会議」で、秀吉は信忠の子・三法師を推したという説がありますが、現在は否定されつつあります。
当主は織田信忠の子・三法師が継ぐことに
織田家の筆頭家老の勝家の面目を保つために後見人を信孝にしたものの、三法師はまだ三才という幼さであったため、跡取り抗争は激化していきます。
清須会議後の信孝~織田家当主の後見人へ
「清須会議」ののち、羽柴秀吉は織田家から養子に来た羽柴秀勝(信長の4男)を喪主にして、大規模な葬儀を執り行います。この葬儀のやり方に、織田信孝や柴田勝家は反発。
しかし、これがきっかけで「信長の後継者は羽柴秀吉」と世間は受け止めるようになりました。
スポンサードリンク
羽柴秀吉と柴田勝家の対立を決定的なものにし、「賤ヶ岳の戦い」が勃発
ここで勝家と信孝は切腹して果て、当主の三法師は信雄が貢献することになりました。実質、織田家の実験を握ったのは信雄…と思われたのですが、そうはいかなかったのです。
力をつけた羽柴秀吉との関係が悪化・領地を没収される…
そもそも、秀吉は信雄に仕える気なんかさらさらありませんでした。なので、「賤ヶ岳の戦い」のあとは両者の関係が悪化し、秀吉は安土城から信雄を追い出すことまでしています。かつての主の子の一人を切腹させ、さらにもう一人は城から追い出し、秀吉がやったことはなかなかえげつないですよね(ちなみに晩年にやったこともかなり酷い)。
秀吉と信雄はついに小牧長久手の戦いへ
秀吉と対立した信雄は、勢力を広げていた徳川家康と組んで秀吉を討とうと奮起(小牧長久手の戦い)。ここで信雄は「無能」という評判はどこにいった?というくらいの奮闘を見せるのですが、羽柴軍の力には及ばず、結果的に和睦しています。しかも、家康に断りもなく和睦…。その後に秀吉は信雄より高い地位につき、かつての主従関係は完全に逆転。秀吉は最初は信雄が大名でいることを許しますが、のちに信雄が持っていた領地をぜんぶ没収してしまいます。家臣が完全に上になっただけでなく、領地まで没収。信長が天でどんなに嘆いたでしょうか…。財産を失った信雄は、家臣もほとんどつかない状態で転々としますが、秀吉の許しを得て「御伽集」に加えられることになりました。秀吉は周りを自分の信用できる人物で固め、天下統一を果たし豊臣政権を樹立します。
スポンサードリンク
秀吉の死後から晩年まで
信雄の人生を見ても「人生とは数奇なものだ」としみじみ感じますが、それは豊臣家も同じでした。天下統一を果たした秀吉でしたが、晩年はようやく生まれた嫡子・秀頼を当主にするために養子たちを冷遇。跡取りとして育てていた秀次も、切腹させてしまいます。これらの所業が諸国の大名たちの反発を買い、秀吉亡き後は徳川家康が勢力を拡大させることになりました。
関ケ原では西軍についた信雄
豊臣家家臣の間で勃発した「関ヶ原の戦い」では、信雄は西軍の石田三成につきます。でも、結果は家康軍の東軍が勝ち、信雄は家康に領地を没収されてしまいました。以前は秀吉に領地を奪われ、今度は家康に奪われ、このあたりも信雄が「無能すぎる」と言われる要因になっているようです。とはいえ、ここでも「織田信長の息子」という血筋が彼を救います。
敗戦後は家康に救われ5万石の領主に
信長の血を引いている信雄の存在を重く見た家康は、新しく5万石の領地を彼に与えました。その後も、「信長の次男」という肩書が彼を守り続け、家康のあとをついで二代目将軍となった徳川秀忠、三代目家光からも大切にされ、老後は豊かに生活したようです。秀吉と争い家康にもにらまれ、信雄はいつ命を落としてもおかしくない人生を送りました。にもかかわらず、江戸時代まで生きて織田家の血をつなぐことができたのは、ひとえに父・織田信長の偉大さのおかげといっても過言ではありません。織田信長の息子を、簡単に殺すことはできない。信長の名声は、死んでからも息子の命を守ったのです。天下統一を果たした豊臣家が一代で滅亡したことを思えば、最終的に勝ったのは織田家と言えるのかもしれませんね。
スポンサードリンク
富岡製糸場と織田信雄
「無能すぎる」という評価が付きまとう信雄ですが、戦以外のところでは優秀さを発揮。信雄が作った「楽山園」という庭園は、国が指定する「名勝(鑑賞の価値が高い場所のこと)」として指定され、彼がはじめた養蚕業は、のちに伊藤博文が「富岡製糸所」を作ることにもつながりました。世界遺産にも認定された「富岡製糸所」と織田家に関りがあるというのは、ちょっと驚きですよね。
織田信雄の家紋「織田木瓜」と副紋「揚羽蝶」
織田信雄が使用していたのは「五つ木瓜」
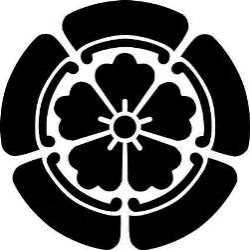
織田木瓜
「織田木瓜」とも言われる家紋で、信長も使用していました。信長が使用していたことから、この家紋は戦国武将の家紋の中でも屈指の知名度と人気があります。木瓜とは中国で官服などに付いていた文様が、日本に伝来し社殿の御廉に用いられるようになったものが文様化したものです。木瓜は子孫繁栄を表し、縁起のよいものとされてきました。五大紋の一つでもあり、北陸地方や東北地方で多く見られます。家紋として取り入れた家は多く、様々な種類の木瓜紋が考案されました。シンプルな木瓜をベースに、剣と合わせた剣木瓜、丸に木瓜、庵の中に入れた庵木瓜、縦に描いた立ち木瓜、菱形をした木瓜菱などバリエーションは豊富です。公家では徳大寺家、武家では新撰組の沖田総司や佐倉藩の堀田氏、岡田藩の伊東氏、出羽の遊佐氏などが使用しています。
副紋は揚羽蝶

揚羽蝶
副紋も、信長も使用していた「揚羽蝶」です。蝶は中国から伝来し、平安時代には様々な分野で使われるようになりました。その証拠として、平家物語や源平盛衰記にも多数登場しています。文様から徐々に家紋に用いられるようになり、平氏一族が使用したことで全国的に広まり、江戸時代には300ほどの幕臣の家紋となりました。織田信長の代表紋は織田瓜ですが、他に揚羽蝶も使用していました。平家の出と称するのに合わせ使用したと言われています。また、平清盛流の者に多く用いられていたため、その後清盛流の代表紋にもなりました。その他の使用者には、武家では伊勢氏、池田氏、松平長沢氏、公家では西洞院氏などがあります。
スポンサードリンク
戦国武将117名の家紋一覧をまとめてチェックしよう
 織田木瓜 織田木瓜 |
 大一大万大吉 大一大万大吉 |
 太閤桐 太閤桐 |
 水色桔梗 水色桔梗 |
| 石田三成 | 豊臣秀吉 | 明智光秀/山県昌景 |
|
 竹に二羽飛び雀/上杉笹 竹に二羽飛び雀/上杉笹 |
 武田菱 武田菱 |
 真田六文銭 真田六文銭 |
 竹に雀/仙台笹 竹に雀/仙台笹 |
| 上杉謙信/上杉景勝/伊達成実 | 武田信玄/武田信繁/武田勝頼/安国寺恵瓊 | 真田幸村/真田昌幸 | 伊達政宗 |
 蛇の目 蛇の目 |
 徳川葵 徳川葵 |
 黒田藤巴 黒田藤巴 |
 向い蝶 向い蝶 |
| 加藤清正 | 徳川家康/徳川秀忠 | 黒田官兵衛/黒田長政 | 大谷 吉継 |
 前田梅鉢/剣梅鉢 |
 一文字三星 一文字三星 |
 池田蝶 池田蝶 |
 足利二つ引き 足利二つ引き |
| 前田利家/前田慶次 | 毛利元就/毛利輝元 | 池田恒興/池田輝政 | 今川義元 |
 丸に立ち葵 丸に立ち葵 |
 九枚笹 九枚笹 |
 二頭立波 二頭立波 |
 二つ雁金 二つ雁金 |
| 本多忠勝 | 竹中半兵衛 | 斎藤道三 | 柴田勝家 |
 丸に竪木瓜 丸に竪木瓜 |
 三つ盛木瓜に剣花菱 三つ盛木瓜に剣花菱 |
 福島沢瀉 福島沢瀉 |
 井伊橘 井伊橘 |
| 滝川一益 | 直江兼続 | 福島正則 | 井伊直虎/井伊直政 |
 鶴丸 鶴丸 |
 丸に細桔梗 丸に細桔梗 |
 丸に七つ片喰 丸に七つ片喰 |
 剣片喰 剣片喰 |
| 森蘭丸/森長可 | 太田道灌 | 長宗我部元親 | 宇喜多秀家 |
 土佐柏 土佐柏 |
 三つ柏 三つ柏 |
 八咫烏 八咫烏 |
 平四つ目結 平四つ目結 |
| 山内一豊 | 島左近 | 雑賀孫一 | 尼子晴久/京極高次 |
 ばら藤に井桁 ばら藤に井桁 |
 丸に違い鎌 丸に違い鎌 |
 蔦 蔦 |
 大友抱き花杏葉 大友抱き花杏葉 |
| 片倉小十郎 | 小早川秀秋 | 藤堂高虎/松永久秀 | 大友宗麟/高橋紹運/立花道雪 |
 中結び祇園守 中結び祇園守 |
 祇園守 祇園守 |
 足利二つ引き 足利二つ引き |
 対い鶴 対い鶴 |
| 小西行長 | 立花宗茂 | 足利尊氏/足利義昭 | 蒲生氏郷 |
 七つ割り隅立て四つ目 七つ割り隅立て四つ目 |
 細川九曜 細川九曜 |
 笹龍胆 笹龍胆 |
 丹羽直違 丹羽直違 |
| 佐々成政 | 細川忠興 細川藤孝 |
源頼朝 | 丹羽長秀 |
 丸に片喰 丸に片喰 |
 榊原源氏車 榊原源氏車 |
 三つ盛り木瓜 三つ盛り木瓜 |
 違い鷹の羽 |
| 酒井忠次 | 榊原康政 | 朝倉義景 | 片桐且元 |
 下がり藤 下がり藤 |
 黒餅 黒餅 |
 北条対い蝶 北条対い蝶 |
 丸に二つ引き 丸に二つ引き |
| 加藤嘉明 | 黒田長政 | 北条早雲 | 最上義光 |
 三つ盛り亀甲に花菱 三つ盛り亀甲に花菱 |
 丸に十文字 丸に十文字 |
 蜂須賀卍 蜂須賀卍 |
 七曜 七曜 |
| 浅井長政 | 島津義弘/島津貴久/島津貴久/島津義久 | 蜂須賀 小六(正勝) | 高山右近/九鬼嘉隆 |
 津軽牡丹 津軽牡丹 |
 北条鱗 北条鱗 |
 丸に上の字 丸に上の字 |
 右三つ巴 右三つ巴 |
| 津軽為信 | 北条氏康/北条氏政 | 村上義清/村上武吉 | 結城秀康/清水宗治/山本勘助/小早川隆景 |
 永楽銭 永楽銭 |
 梅鉢 梅鉢 |
 変わり十二日足 変わり十二日足 |
 丸に三つ引き 丸に三つ引き |
| 仙石秀久 | 筒井順慶 | 龍造寺隆信 | 吉川広家 |
 丸に違い鷹の羽 丸に違い鷹の羽 |
 五七桐 五七桐 |
 生駒車 生駒車 |
 九条下がり藤 九条下がり藤 |
| 浅野幸長/浅野長政 | 豊臣秀次/斎藤義龍/豊臣秀長 | 生駒正俊 | 本願寺顕如 |
 丸に揚羽蝶 丸に揚羽蝶 |
 吾亦紅/地楡に雀 吾亦紅/地楡に雀 |
 丸に三つ葵 丸に三つ葵 |
 輪違い 輪違い |
| 平清盛 | 柳生宗矩 | 松平忠吉 | 脇坂安治 |
 鍋島花杏葉 鍋島花杏葉 |
 結城巴 結城巴 |
 揚羽蝶 揚羽蝶 |
 唐花紋 唐花紋 |
| 鍋島勝茂 | 松平忠直 | 吉川元春 | 陶晴賢 |
 抱き茗荷 抱き茗荷 |
 五本骨扇に月丸 五本骨扇に月丸 |
||
| 堀尾吉晴 | 佐竹義重 |
スポンサードリンク
| 他にもあるぞ!超人気家紋コンテンツ |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |