戦国時代を振り返ってみると、時勢を大きく変えるいくつかの出来事があります。中でも有名なのが織田信長が明智光秀に討たれた「本能寺の変」でしょう。それまでの常識を打ち破る政策を次々と実行し、「天下をとるかも」と言われていた武田勝頼(武田信玄の息子)を破った織田信長は、「もっとも天下統一に近い武将」とされていました。というより、おそらく多くの人が「織田信長が天下統一をとるだろう」と思っていたはずです。
スポンサードリンク
目次
|
|
|
安国寺恵瓊は信長が天下をとれないことを予想していた?
その信長が「本能寺の変」で討たれたことは、当時の時代の流れをひっくり返すような出来事でした。信長が死んだことで、運命が変わってしまった武将もたくさんいたのです。その中で、「信長の勢いは3、5年。そのあとに公家になり、仰向けに転ぶだろう」と予言していた人物がいます。それが安国寺恵瓊(あんこくじえけい)です。
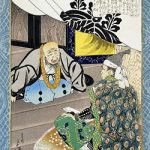
1573年の手紙で語られる信長の衰退
恵瓊はこのことを1573年に書いた手紙の中で語っており、そのほぼ10年後にあたる1583年に信長は本能寺の変で討死しました。また、手紙の中で恵瓊は秀吉の素質を見抜いてほめたたえており、まるで豊臣政権の訪れを予想していたかのようです。このように、「先を読む力」に大変優れていた安国寺恵瓊はどんな人物だったのでしょうか?
誰もが認める優秀な交渉人・安国寺恵瓊
安国寺恵瓊は、中国地方の大名・毛利家で軍師として活躍していた人物です。
毛利家と宇喜多家との同盟を提案
日に日に大きな勢力となっていく織田信長に対抗するために、恵瓊は中国地方の毛利家と、備前(今の岡山)を治めていた宇喜多家の同盟を提案。毛利家を中心に中国地方の勢力を強めることに成功しました。ちなみに、播磨(今の兵庫県)は信長側の黒田官兵衛がいる地域で、毛利家と宇喜多家の同盟は官兵衛をけん制することにもつながりました。時代を読んでこそ、毛利家・宇喜多家が協力して立ち向かうことが必要と考えたのでしょう。
スポンサードリンク
毛利家を裏切り秀吉の家臣となる恵瓊
しかし、その後に毛利家と秀吉が戦った時には毛利家を見限り、秀吉の家臣となっています。これにより、かつて争っていた官兵衛と恵瓊は肩を並べて秀吉のもとで働くようになりました。
これからは秀吉の時代である…そう呼んでいたからこそ、恵瓊は毛利家から秀吉のもとへ行ったのでしょう。
恵瓊でも読めなかった関ケ原~敗北から斬首へ
しかし、その恵瓊でも読めなかったことがありました。それは「関ヶ原の戦い」の結末です。秀吉亡き後に徳川家康と石田三成の間で勃発した「関ヶ原の戦い」の中で、恵瓊は前に仕えていた毛利家に交渉。そして、毛利輝元を西軍の総大将として担ぎ出しました。※「関ヶ原の戦い」だと石田三成が総大将のように語られますが、三成は参謀です。が、輝元は実際には関が原には出ていませんし、三成と家康の戦いと考えていいでしょう。当時、「関ヶ原の戦い」では「西軍が有利」とされており、恵瓊もそう考えていたのでしょう。しかし、西軍は度重なる味方の裏切りから総崩れになり、敗北。
スポンサードリンク
関ケ原の敗戦で処刑された安国寺恵瓊
恵瓊は輝元を総大将にするために交渉したことが原因で、斬首の刑になりました。関ヶ原の戦いでは、石田三成・小西行長、そしこの安国寺恵瓊が六条河原で処刑されました。「信長は天下をとれない」という予想を的中させた恵瓊ですが、関ヶ原の先にある自分の未来をみることはできなかったようです。亡くなった年齢は62歳とも、64歳とも言われています。
安国寺恵瓊の家紋は「武田菱」、つまり武田家の子孫だった
恵瓊が使用していた家紋は、武田信玄で有名な「武田家」が使用していた武田菱です。

なぜ恵瓊が、武田家が使用している武田菱?と思われるかもしれませんが、ここにはちゃんと理由があります。恵瓊は、武田家の14代目当主・武田信重の子どもなのです。信長の未来を予想したと言われる恵瓊ですが、その優秀さも信玄公を生んだ武田氏の流れと考えれば納得ですね。
菱紋は、菱形の幾何学的な紋の総称です。古代から世界中で見られた文様で、植物であるヒシの実に由来していると言われていますが詳細は不明です。土器にも鱗と同様刻まれていることから、呪術的な意味もあったと考えられています。家紋としては人気があった代表的な紋で、一つから最大で十六個の菱を組み合わせ、バリエーションは様々ありました。また、配列や向きを変えたものなどがあり、江戸時代には幕臣約150の家紋に用いられたと言われています。有名なものは、甲斐源氏や信濃源氏一族に用いられた「割菱」、小笠原家の「三階菱」などです。武家の使用者は他に、高杉晋作、松前氏、武田氏、市橋氏、三好氏、大内氏、山口氏などです。
スポンサードリンク
戦国武将117名の家紋一覧をまとめてチェックしよう
 織田木瓜 織田木瓜 |
 大一大万大吉 大一大万大吉 |
 太閤桐 太閤桐 |
 水色桔梗 水色桔梗 |
| 石田三成 | 豊臣秀吉 | 明智光秀/山県昌景 |
|
 竹に二羽飛び雀/上杉笹 竹に二羽飛び雀/上杉笹 |
 武田菱 武田菱 |
 真田六文銭 真田六文銭 |
 竹に雀/仙台笹 竹に雀/仙台笹 |
| 上杉謙信/上杉景勝/伊達成実 | 武田信玄/武田信繁/武田勝頼/安国寺恵瓊 | 真田幸村/真田昌幸 | 伊達政宗 |
 蛇の目 蛇の目 |
 徳川葵 徳川葵 |
 黒田藤巴 黒田藤巴 |
 向い蝶 向い蝶 |
| 加藤清正 | 徳川家康/徳川秀忠 | 黒田官兵衛/黒田長政 | 大谷 吉継 |
 前田梅鉢/剣梅鉢 |
 一文字三星 一文字三星 |
 池田蝶 池田蝶 |
 足利二つ引き 足利二つ引き |
| 前田利家/前田慶次 | 毛利元就/毛利輝元 | 池田恒興/池田輝政 | 今川義元 |
 丸に立ち葵 丸に立ち葵 |
 九枚笹 九枚笹 |
 二頭立波 二頭立波 |
 二つ雁金 二つ雁金 |
| 本多忠勝 | 竹中半兵衛 | 斎藤道三 | 柴田勝家 |
 丸に竪木瓜 丸に竪木瓜 |
 三つ盛木瓜に剣花菱 三つ盛木瓜に剣花菱 |
 福島沢瀉 福島沢瀉 |
 井伊橘 井伊橘 |
| 滝川一益 | 直江兼続 | 福島正則 | 井伊直虎/井伊直政 |
 鶴丸 鶴丸 |
 丸に細桔梗 丸に細桔梗 |
 丸に七つ片喰 丸に七つ片喰 |
 剣片喰 剣片喰 |
| 森蘭丸/森長可 | 太田道灌 | 長宗我部元親 | 宇喜多秀家 |
 土佐柏 土佐柏 |
 三つ柏 三つ柏 |
 八咫烏 八咫烏 |
 平四つ目結 平四つ目結 |
| 山内一豊 | 島左近 | 雑賀孫一 | 尼子晴久/京極高次 |
 ばら藤に井桁 ばら藤に井桁 |
 丸に違い鎌 丸に違い鎌 |
 蔦 蔦 |
 大友抱き花杏葉 大友抱き花杏葉 |
| 片倉小十郎 | 小早川秀秋 | 藤堂高虎/松永久秀 | 大友宗麟/高橋紹運/立花道雪 |
 中結び祇園守 中結び祇園守 |
 祇園守 祇園守 |
 足利二つ引き 足利二つ引き |
 対い鶴 対い鶴 |
| 小西行長 | 立花宗茂 | 足利尊氏/足利義昭 | 蒲生氏郷 |
 七つ割り隅立て四つ目 七つ割り隅立て四つ目 |
 細川九曜 細川九曜 |
 笹龍胆 笹龍胆 |
 丹羽直違 丹羽直違 |
| 佐々成政 | 細川忠興 細川藤孝 |
源頼朝 | 丹羽長秀 |
 丸に片喰 丸に片喰 |
 榊原源氏車 榊原源氏車 |
 三つ盛り木瓜 三つ盛り木瓜 |
 違い鷹の羽 |
| 酒井忠次 | 榊原康政 | 朝倉義景 | 片桐且元 |
 下がり藤 下がり藤 |
 黒餅 黒餅 |
 北条対い蝶 北条対い蝶 |
 丸に二つ引き 丸に二つ引き |
| 加藤嘉明 | 黒田長政 | 北条早雲 | 最上義光 |
 三つ盛り亀甲に花菱 三つ盛り亀甲に花菱 |
 丸に十文字 丸に十文字 |
 蜂須賀卍 蜂須賀卍 |
 七曜 七曜 |
| 浅井長政 | 島津義弘/島津貴久/島津貴久/島津義久 | 蜂須賀 小六(正勝) | 高山右近/九鬼嘉隆 |
 津軽牡丹 津軽牡丹 |
 北条鱗 北条鱗 |
 丸に上の字 丸に上の字 |
 右三つ巴 右三つ巴 |
| 津軽為信 | 北条氏康/北条氏政 | 村上義清/村上武吉 | 結城秀康/清水宗治/山本勘助/小早川隆景 |
 永楽銭 永楽銭 |
 梅鉢 梅鉢 |
 変わり十二日足 変わり十二日足 |
 丸に三つ引き 丸に三つ引き |
| 仙石秀久 | 筒井順慶 | 龍造寺隆信 | 吉川広家 |
 丸に違い鷹の羽 丸に違い鷹の羽 |
 五七桐 五七桐 |
 生駒車 生駒車 |
 九条下がり藤 九条下がり藤 |
| 浅野幸長/浅野長政 | 豊臣秀次/斎藤義龍/豊臣秀長 | 生駒正俊 | 本願寺顕如 |
 丸に揚羽蝶 丸に揚羽蝶 |
 吾亦紅/地楡に雀 吾亦紅/地楡に雀 |
 丸に三つ葵 丸に三つ葵 |
 輪違い 輪違い |
| 平清盛 | 柳生宗矩 | 松平忠吉 | 脇坂安治 |
 鍋島花杏葉 鍋島花杏葉 |
 結城巴 結城巴 |
 揚羽蝶 揚羽蝶 |
 唐花紋 唐花紋 |
| 鍋島勝茂 | 松平忠直 | 吉川元春 | 陶晴賢 |
 抱き茗荷 抱き茗荷 |
 五本骨扇に月丸 五本骨扇に月丸 |
||
| 堀尾吉晴 | 佐竹義重 |
スポンサードリンク
| 他にもあるぞ!超人気家紋コンテンツ |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |


