鍋島勝茂は肥前佐賀藩初代藩主となったことで良く知られる武将ですが、実は彼よりも父の直茂の方が有名です。直茂は、肥前を治めていた龍造寺隆信という武将に仕えていた人物。頭脳明晰な人物として知られる直茂は、九州の大きな勢力であった大友家と隆信の戦いを勝利に導く作戦を立てているほか、隆信が亡くなったあとは島津氏に仕えながらも豊臣家と連携するなどして、鍋島家の存在を大きく躍進させています。その勢いは主の龍造寺家をもしのぐほど。
スポンサードリンク
目次
|
|
|
頭脳明晰で知られる鍋島直茂の息子・勝茂
秀吉は龍造寺家よりも鍋島直茂を高く評価
秀吉は龍造寺家の当主であった龍造寺高房よりも直茂の能力を買っており、「肥前の大名は事実上鍋島直茂であっった」と考えて間違いありません。秀吉の朝鮮出兵の総大将が直茂であったことからも、それは明らかです。
「関ヶ原の戦い」で見えた勝茂の本気
その直茂の子・勝茂が活躍したのは「関ヶ原の戦い」でした。勝茂は当初、石田三成率いる西軍に参加する予定でしたが、「東軍が勝つ」と読んでいた父・直茂は「西軍を抜けて東軍の徳川家康につくように」と言いました。これを受け入れた勝茂は、関ヶ原の戦いの本戦開始前に西軍参加をとりやめ、徳川家康の東軍で闘うことを決意します。そのために大阪の屋敷に戻り、家康に忠誠心を見せるために「家の者全員で切腹して見せる」とまで言っています。家康はこの勝茂の行動を大いに気に入り、戦で九州の武将たちを攻撃することを条件に東軍に加えました。頭脳明晰な父が活躍する一方、勝茂もこうして潔さを見せることで鍋島家を存続させたのです。
鍋島化け猫騒動について
こうした活躍もあって、鍋島勝茂は主での龍造寺家を抜く形で肥前佐賀藩初代藩主になっています。戦国の世にありながら、鍋島家は龍造寺家と争うことなく大名となりましたが、それでも「主を裏切った、利用した」などと悪く言われることも多く、それは歌舞伎の題材になるほど。※1968年には「呪いの沼」というタイトルでこのことが映画化されました(しかし、実際の史実とはかなり内容が異なります)。
スポンサードリンク
造寺家当主・高房も死亡
大名の座を鍋島家に渡すことを拒んだ龍造寺家当主・高房は、直茂の養女でもあった妻を殺害して自分も自殺未遂をし、その後に実際に亡くなっています。この死にショックを受けたのか、高房の父も亡くなってしまいました。無念のうちに亡くなった高房の心情を思う人が多かったのか、高房が死後に白装束をまとって城下町を馬で走っているという噂が流れました。これが「高房が飼っていた猫が化けて出て、直茂と勝茂を呪ったという伝説になっています。勝茂の父・直茂は、晩年に耳の病気を患い苦しみ抜いて亡くなったそうで、これもまた「呪い」と言われる要因になったとか。
ただ、家臣が主と争うことが当たり前の戦国時代で、恨みを買いつつも主と戦うことはしなかった鍋島直茂と勝茂は、龍造寺家にきちんとした敬意も持っていたのではないでしょうか。
直茂が藩主となってもおかしくなかったところを、息子の勝茂にしたのも配慮のためと言われています(ただ、直茂が高齢であったためという話しもあります)。
鍋島家の家紋は「鍋島花杏葉」
鍋島勝茂が使用していた家紋は、「鍋島花杏葉」です。
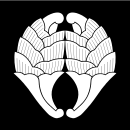
この家紋は、勝茂の父・直茂が九州の有力者であった大友家の軍を破った時に得たもので、以来鍋島家ではこの家紋を定紋にしています。九州で知らないものはいないと言われた大友家の家紋は、多くの武将にとってあこがれの存在でした。その大友家を破った証として、鍋島家はこの家紋を掲げるようになったのです。大友家と言えば大友宗麟が有名ですが、その勢いがどれだけ凄かったのかが解るエピソードです。
スポンサードリンク
戦国武将117名の家紋一覧をまとめてチェックしよう
 織田木瓜 織田木瓜 |
 大一大万大吉 大一大万大吉 |
 太閤桐 太閤桐 |
 水色桔梗 水色桔梗 |
| 石田三成 | 豊臣秀吉 | 明智光秀/山県昌景 |
|
 竹に二羽飛び雀/上杉笹 竹に二羽飛び雀/上杉笹 |
 武田菱 武田菱 |
 真田六文銭 真田六文銭 |
 竹に雀/仙台笹 竹に雀/仙台笹 |
| 上杉謙信/上杉景勝/伊達成実 | 武田信玄/武田信繁/武田勝頼/安国寺恵瓊 | 真田幸村/真田昌幸 | 伊達政宗 |
 蛇の目 蛇の目 |
 徳川葵 徳川葵 |
 黒田藤巴 黒田藤巴 |
 向い蝶 向い蝶 |
| 加藤清正 | 徳川家康/徳川秀忠 | 黒田官兵衛/黒田長政 | 大谷 吉継 |
 前田梅鉢/剣梅鉢 |
 一文字三星 一文字三星 |
 池田蝶 池田蝶 |
 足利二つ引き 足利二つ引き |
| 前田利家/前田慶次 | 毛利元就/毛利輝元 | 池田恒興/池田輝政 | 今川義元 |
 丸に立ち葵 丸に立ち葵 |
 九枚笹 九枚笹 |
 二頭立波 二頭立波 |
 二つ雁金 二つ雁金 |
| 本多忠勝 | 竹中半兵衛 | 斎藤道三 | 柴田勝家 |
 丸に竪木瓜 丸に竪木瓜 |
 三つ盛木瓜に剣花菱 三つ盛木瓜に剣花菱 |
 福島沢瀉 福島沢瀉 |
 井伊橘 井伊橘 |
| 滝川一益 | 直江兼続 | 福島正則 | 井伊直虎/井伊直政 |
 鶴丸 鶴丸 |
 丸に細桔梗 丸に細桔梗 |
 丸に七つ片喰 丸に七つ片喰 |
 剣片喰 剣片喰 |
| 森蘭丸/森長可 | 太田道灌 | 長宗我部元親 | 宇喜多秀家 |
 土佐柏 土佐柏 |
 三つ柏 三つ柏 |
 八咫烏 八咫烏 |
 平四つ目結 平四つ目結 |
| 山内一豊 | 島左近 | 雑賀孫一 | 尼子晴久/京極高次 |
 ばら藤に井桁 ばら藤に井桁 |
 丸に違い鎌 丸に違い鎌 |
 蔦 蔦 |
 大友抱き花杏葉 大友抱き花杏葉 |
| 片倉小十郎 | 小早川秀秋 | 藤堂高虎/松永久秀 | 大友宗麟/高橋紹運/立花道雪 |
 中結び祇園守 中結び祇園守 |
 祇園守 祇園守 |
 足利二つ引き 足利二つ引き |
 対い鶴 対い鶴 |
| 小西行長 | 立花宗茂 | 足利尊氏/足利義昭 | 蒲生氏郷 |
 七つ割り隅立て四つ目 七つ割り隅立て四つ目 |
 細川九曜 細川九曜 |
 笹龍胆 笹龍胆 |
 丹羽直違 丹羽直違 |
| 佐々成政 | 細川忠興 細川藤孝 |
源頼朝 | 丹羽長秀 |
 丸に片喰 丸に片喰 |
 榊原源氏車 榊原源氏車 |
 三つ盛り木瓜 三つ盛り木瓜 |
 違い鷹の羽 |
| 酒井忠次 | 榊原康政 | 朝倉義景 | 片桐且元 |
 下がり藤 下がり藤 |
 黒餅 黒餅 |
 北条対い蝶 北条対い蝶 |
 丸に二つ引き 丸に二つ引き |
| 加藤嘉明 | 黒田長政 | 北条早雲 | 最上義光 |
 三つ盛り亀甲に花菱 三つ盛り亀甲に花菱 |
 丸に十文字 丸に十文字 |
 蜂須賀卍 蜂須賀卍 |
 七曜 七曜 |
| 浅井長政 | 島津義弘/島津貴久/島津貴久/島津義久 | 蜂須賀 小六(正勝) | 高山右近/九鬼嘉隆 |
 津軽牡丹 津軽牡丹 |
 北条鱗 北条鱗 |
 丸に上の字 丸に上の字 |
 右三つ巴 右三つ巴 |
| 津軽為信 | 北条氏康/北条氏政 | 村上義清/村上武吉 | 結城秀康/清水宗治/山本勘助/小早川隆景 |
 永楽銭 永楽銭 |
 梅鉢 梅鉢 |
 変わり十二日足 変わり十二日足 |
 丸に三つ引き 丸に三つ引き |
| 仙石秀久 | 筒井順慶 | 龍造寺隆信 | 吉川広家 |
 丸に違い鷹の羽 丸に違い鷹の羽 |
 五七桐 五七桐 |
 生駒車 生駒車 |
 九条下がり藤 九条下がり藤 |
| 浅野幸長/浅野長政 | 豊臣秀次/斎藤義龍/豊臣秀長 | 生駒正俊 | 本願寺顕如 |
 丸に揚羽蝶 丸に揚羽蝶 |
 吾亦紅/地楡に雀 吾亦紅/地楡に雀 |
 丸に三つ葵 丸に三つ葵 |
 輪違い 輪違い |
| 平清盛 | 柳生宗矩 | 松平忠吉 | 脇坂安治 |
 鍋島花杏葉 鍋島花杏葉 |
 結城巴 結城巴 |
 揚羽蝶 揚羽蝶 |
 唐花紋 唐花紋 |
| 鍋島勝茂 | 松平忠直 | 吉川元春 | 陶晴賢 |
 抱き茗荷 抱き茗荷 |
 五本骨扇に月丸 五本骨扇に月丸 |
||
| 堀尾吉晴 | 佐竹義重 |
スポンサードリンク
| 他にもあるぞ!超人気家紋コンテンツ |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |


