武将でありながらキリシタンでもあった、そんな異色の経歴を持つのが小西行長です。キリシタンであることが良く知られているため、そちらばかりがクローズアップされがちなのですが、実は彼は経歴も異例。なんと、彼はもともとは武士ではなく堺ではたらく商人でした。そんな小西行長の家紋について、また彼の壮絶と言える人生について解説していきます。
スポンサードリンク
目次
|
|
|
当時の堺は、日本有数の商業都市

その堺で、九州との貿易を積極的におこなっていたのが「日比屋家」という家です。この日比屋家と小西家は婚姻関係でつながりがあり、大変に豊かな生活をしていたことが想像できます。大都市で貿易を営む家が、貧しいはずがないですからね。そして、貿易という生業がそうさせたのか両家ともキリシタンでした。もちろん、そこで生まれた行長もキリシタンです。さらに、行長はキリシタンという立場を利用しつつ、「キリシタンしか使うことができない独自の貿易」も行っていた様で、かなり深いつながりをもっていたと考えられています。
豊臣秀吉と出会う行長
その行長が、どうして豊臣秀吉と出会ったのかはよくわかっていません。もともとは宇喜多家に仕えていたことが解っているので、そこで秀吉と何らかの縁があったのではないか?とも言われています。とにかく、秀吉の命を受けた行長は、25歳で小豆島を管轄することになりました。その後も秀吉と共に四国に攻め入るなど、豊臣軍として武勲をあげています。
スポンサードリンク
秀吉のバテレン追放令でキリシタンが一蹴される!?
秀吉は後に「バテレン追放令」を出してキリシタンを一蹴することを考えますが、行長は秀吉に仕えつつも、キリシタンをかくまって貿易を続けました。当時のイエスズ会は日本の貿易市場を独占している状態だったので、行長はそのつながりを守ることでこれまでの貿易を存続させたのです。このような努力が認められ、行長は加藤清正と共に肥後の国を与えられ、12万石を所有する武将となっています。仲が悪かった清正と共に…というところに因果を感じますね。生まれた時の環境から、彼がキリシタンになるのは当たり前の流れでした。しかし、彼は親兄弟に言われたからキリシタンになったのではなく、自らがその教えに惹かれていたのだと思わせるエピソードがあります。
関ケ原の戦いでは西軍に就く行長
秀吉亡き後に勃発した関ヶ原の戦いで、行長は石田三成率いる西軍に参加します。しかし、味方の裏切り行為もあり徳川家康率いる東軍が勝利し、西軍は敗北してしまいました。武将であれば、たとえ敵将に捕まっても切腹を選んで死ぬことが美徳とされています。しかし、キリシタンだった彼は自ら死ぬことを拒み、斬首で命を終えました。神に仕える彼は、武将としてではなくキリシタンとして死ぬことを選んだのかもしれませんね。
キリシタン大名・小西行長の家紋とは?
中結祇園守紋:小西行長の家紋その1

キリシタンの印象が強い小西行長ですが、彼にもちゃんと家紋があります。彼の家紋は「中結祇園守(なかむすびぎおんまもり)」。とても美しく、どことなく行長の誠実な人柄が伝わってくるような気がしますね。こちらの「祇園守」は八坂神社が作ったお守りがもとになっているそう。中央に見える棒のようなものは巻物です。
スポンサードリンク
華久留子紋:小西行長の家紋その2
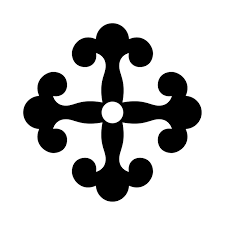
そして、もうひとつが「華久留子」。「久留子」は、当時のキリシタンの言葉で「クロス」を意味しました。見てのとおり、十字架の形をした家紋です。キリシタンとしての生き方を通した行長らしい家紋ですね。キリシタンは弾圧された時代があり、表だって布教活動などはできませんでしたが、それでもキリシタンたちはこうして家紋に十字架を取り入れることでキリスト教を守り続けたと言います。なんとも行長らしい、彼の人生がそのまま形になった様な家紋ですね。
最期の死に方はとても武将らしい行長と、その人生

キリシタンとしての人生を歩みながら、同時に武将として生きた行長。最期に彼は切腹を拒んで斬首となりましたが、直前まで凛とした視線を忘れず、その姿に誰もが敬意を抱いたと語られています。それが武将としての在り方であったのか、キリシタンとして神のためにという信仰からだったのかは解りませんが、行長が誇り高き武将であったことはよくわかります。嫡子も一緒に処刑されてしまったため、小西家は断絶となってしまっています。しかし、商人から武将にまでのぼりつめ、さらにキリシタンとしての生き方を全うした彼の人生は、後世で長く語られることなります。
スポンサードリンク
戦国武将117名の家紋一覧をまとめてチェックしよう
 織田木瓜 織田木瓜 |
 大一大万大吉 大一大万大吉 |
 太閤桐 太閤桐 |
 水色桔梗 水色桔梗 |
| 石田三成 | 豊臣秀吉 | 明智光秀/山県昌景 |
|
 竹に二羽飛び雀/上杉笹 竹に二羽飛び雀/上杉笹 |
 武田菱 武田菱 |
 真田六文銭 真田六文銭 |
 竹に雀/仙台笹 竹に雀/仙台笹 |
| 上杉謙信/上杉景勝/伊達成実 | 武田信玄/武田信繁/武田勝頼/安国寺恵瓊 | 真田幸村/真田昌幸 | 伊達政宗 |
 蛇の目 蛇の目 |
 徳川葵 徳川葵 |
 黒田藤巴 黒田藤巴 |
 向い蝶 向い蝶 |
| 加藤清正 | 徳川家康/徳川秀忠 | 黒田官兵衛/黒田長政 | 大谷 吉継 |
 前田梅鉢/剣梅鉢 |
 一文字三星 一文字三星 |
 池田蝶 池田蝶 |
 足利二つ引き 足利二つ引き |
| 前田利家/前田慶次 | 毛利元就/毛利輝元 | 池田恒興/池田輝政 | 今川義元 |
 丸に立ち葵 丸に立ち葵 |
 九枚笹 九枚笹 |
 二頭立波 二頭立波 |
 二つ雁金 二つ雁金 |
| 本多忠勝 | 竹中半兵衛 | 斎藤道三 | 柴田勝家 |
 丸に竪木瓜 丸に竪木瓜 |
 三つ盛木瓜に剣花菱 三つ盛木瓜に剣花菱 |
 福島沢瀉 福島沢瀉 |
 井伊橘 井伊橘 |
| 滝川一益 | 直江兼続 | 福島正則 | 井伊直虎/井伊直政 |
 鶴丸 鶴丸 |
 丸に細桔梗 丸に細桔梗 |
 丸に七つ片喰 丸に七つ片喰 |
 剣片喰 剣片喰 |
| 森蘭丸/森長可 | 太田道灌 | 長宗我部元親 | 宇喜多秀家 |
 土佐柏 土佐柏 |
 三つ柏 三つ柏 |
 八咫烏 八咫烏 |
 平四つ目結 平四つ目結 |
| 山内一豊 | 島左近 | 雑賀孫一 | 尼子晴久/京極高次 |
 ばら藤に井桁 ばら藤に井桁 |
 丸に違い鎌 丸に違い鎌 |
 蔦 蔦 |
 大友抱き花杏葉 大友抱き花杏葉 |
| 片倉小十郎 | 小早川秀秋 | 藤堂高虎/松永久秀 | 大友宗麟/高橋紹運/立花道雪 |
 中結び祇園守 中結び祇園守 |
 祇園守 祇園守 |
 足利二つ引き 足利二つ引き |
 対い鶴 対い鶴 |
| 小西行長 | 立花宗茂 | 足利尊氏/足利義昭 | 蒲生氏郷 |
 七つ割り隅立て四つ目 七つ割り隅立て四つ目 |
 細川九曜 細川九曜 |
 笹龍胆 笹龍胆 |
 丹羽直違 丹羽直違 |
| 佐々成政 | 細川忠興 細川藤孝 |
源頼朝 | 丹羽長秀 |
 丸に片喰 丸に片喰 |
 榊原源氏車 榊原源氏車 |
 三つ盛り木瓜 三つ盛り木瓜 |
 違い鷹の羽 |
| 酒井忠次 | 榊原康政 | 朝倉義景 | 片桐且元 |
 下がり藤 下がり藤 |
 黒餅 黒餅 |
 北条対い蝶 北条対い蝶 |
 丸に二つ引き 丸に二つ引き |
| 加藤嘉明 | 黒田長政 | 北条早雲 | 最上義光 |
 三つ盛り亀甲に花菱 三つ盛り亀甲に花菱 |
 丸に十文字 丸に十文字 |
 蜂須賀卍 蜂須賀卍 |
 七曜 七曜 |
| 浅井長政 | 島津義弘/島津貴久/島津貴久/島津義久 | 蜂須賀 小六(正勝) | 高山右近/九鬼嘉隆 |
 津軽牡丹 津軽牡丹 |
 北条鱗 北条鱗 |
 丸に上の字 丸に上の字 |
 右三つ巴 右三つ巴 |
| 津軽為信 | 北条氏康/北条氏政 | 村上義清/村上武吉 | 結城秀康/清水宗治/山本勘助/小早川隆景 |
 永楽銭 永楽銭 |
 梅鉢 梅鉢 |
 変わり十二日足 変わり十二日足 |
 丸に三つ引き 丸に三つ引き |
| 仙石秀久 | 筒井順慶 | 龍造寺隆信 | 吉川広家 |
 丸に違い鷹の羽 丸に違い鷹の羽 |
 五七桐 五七桐 |
 生駒車 生駒車 |
 九条下がり藤 九条下がり藤 |
| 浅野幸長/浅野長政 | 豊臣秀次/斎藤義龍/豊臣秀長 | 生駒正俊 | 本願寺顕如 |
 丸に揚羽蝶 丸に揚羽蝶 |
 吾亦紅/地楡に雀 吾亦紅/地楡に雀 |
 丸に三つ葵 丸に三つ葵 |
 輪違い 輪違い |
| 平清盛 | 柳生宗矩 | 松平忠吉 | 脇坂安治 |
 鍋島花杏葉 鍋島花杏葉 |
 結城巴 結城巴 |
 揚羽蝶 揚羽蝶 |
 唐花紋 唐花紋 |
| 鍋島勝茂 | 松平忠直 | 吉川元春 | 陶晴賢 |
 抱き茗荷 抱き茗荷 |
 五本骨扇に月丸 五本骨扇に月丸 |
||
| 堀尾吉晴 | 佐竹義重 |
スポンサードリンク
| 他にもあるぞ!超人気家紋コンテンツ |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |


