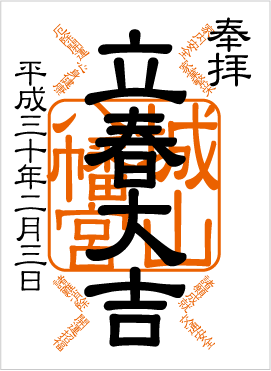最近では少なくなってきたかもしれませんが、「立春大吉」と書かれた紙が門や玄関口に貼られているのを見かけたことがあるという方も多いのではないでしょうか?
いかにも縁起のよさそうな字面なのですが、ここでは立春大吉の意味やお札の正しい貼り方などについてご紹介していきたいと思います。
スポンサードリンク
目次
|
|
|
立春大吉とは?
立春の日、禅寺では「立春大吉」を書いた紙を門に貼る習慣があります。
一般のご家庭でも見られることがあるのは、いわゆる檀家さんだからです。禅寺の習慣のひとつなのですが、「立春大吉」と書かれた紙を貼ることによって厄除けをするのです。
スポンサードリンク
立春大吉のお札について
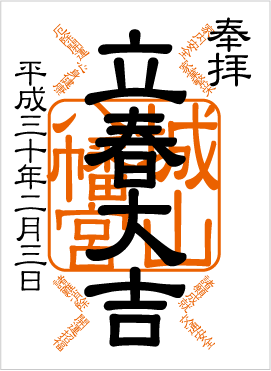
引用:http://www.shiroyama.or.jp/
立春大吉のお札を貼ることによって厄除けになるということなのですが、なぜ厄除けになるのかというと立春大吉という文字に秘密があります。
いかにも縁起がよさそうな字面であるのはもちろんなのですが、立春大吉を縦書きにすると左右対称になります。
裏から見ても表から見ても、立春大吉と読めるかと思います。
この立春大吉と書かれたお札を門や玄関などに貼っておくと、仮に鬼が入ってきても立春大吉のお札を目にすることによって「あれ、この家には入ってなかったっけ?」と勘違いをして逆に出て行ってしまうのです。
裏から読んでも表から読んでも同じ立春大吉で鬼を混乱させ、出て行かせることによって1年を平穏無事に過ごせるというわけです。
かつての旧暦では立春は1年の始まりとされていましたので、そう考えると納得です。
スポンサードリンク
日急急如律令の意味
立春大吉のお札を見ていると、「立春大吉日救急如律令」と書かれているものがあるのに気づくかと思います。
これは「これまでのものを切り、一新していく」「運を急に立ち上げる」といった意味が込められているそうです。
正しい貼り方
立春大吉のお札の正しい貼り方なのですが、まず目線よりも高いところに貼ることと立春の日に貼ることです。
お札を貼る場所に関しては諸説あるようで、以下のような場所が挙げられます。
- 玄関に向かって右側玄
- 関に入ってすぐの柱
- 鬼門
他にも神棚に供えるといったケースもあるようです。
地域によって違いがあるかと思いますので、お住まいの地域ではどうしているのか聞いてみるといいでしょう。
スポンサードリンク
いつまで張るの?
立春大吉のお札は立春の日に貼って、1年間貼り続けます。
つまり、貼りかえるのは次の年の立春ということになります。
一緒にもらう鎮防火燭
立春大吉のお札をもらうとき、一緒に鎮防火燭のお札をもらうことが多くなるかと思います。
鎮防火燭は「火の用心」「悪いことを払う」といった意味が込められているのですが、立春大吉のお札と一緒に立春の日に貼るようにしましょう。
ただ、貼る場所が違ってきます。
- 玄関に向かって左側に貼って立春大吉のお札と対になるように貼る
- キッチンの目線の位置に貼る
といいと言われています。
ちなみに、立春大吉のお札にしても鎮防火燭のお札にしてもお札に直接テープを貼り付けたり画鋲をさしたりするのはNGです。
お札は丁寧に扱いましょう。
スポンサードリンク
立春大吉餅について
立春大吉餅というのは、朔日餅(ついたちもち)のひとつです。
朔日餅というのは有名な和菓子店「赤福」が地域の風習である朔日参りにちなんで1月以外の毎月1日に販売するお餅のことで、2月の立春大吉餅は黒豆と打豆を使った2種類の豆大福となっています。
24節気・72候のまとめカレンダー

太陽の動きをもとに、1年を二十四に分けた「二十四節気」は、季節の指標となる大切な暦であり、古代中国が発祥です。
立春、立夏、立秋、立冬を区切りに4つの節気を設定し、それぞれの季節を更に6等分することで、正しく季節を把握するために使われてきました。
| 24節気 | 2021年 | 72候 |
| 立春 | 2月3日 | 東風解凍,黄鶯睍睆,魚上氷 |
| 雨水 | 2月18日 | 土脉潤起,霞始靆,草木萠動 |
| 啓蟄 | 3月5日 | 蟄虫啓戸,桃始笑,菜虫化蝶 |
| 春分 | 3月20日 | 雀始巣,桜始開,雷乃発声 |
| 清明 | 4月4日 | 玄鳥至,鴻雁北,虹始見 |
| 穀雨 | 4月20日 | 葭始生,霜止出苗,牡丹華 |
| 立夏 | 5月5日 | 蛙始鳴,蚯蚓出,竹笋生 |
| 小満 | 5月21日 | 蚕起食桑,紅花栄,麦秋至 |
| 芒種 | 6月5日 | 螳螂生,腐草為蛍,梅子黄 |
| 夏至 | 6月21日 | 乃東枯,菖蒲華,半夏生 |
| 小暑 | 7月7日 | 温風至,蓮始開,鷹乃学習 |
| 大暑 | 7月22日 | 桐始結花,土潤溽暑,大雨時行 |
| 立秋 | 8月7日 | 涼風至,寒蝉鳴,蒙霧升降 |
| 処暑 | 8月23日 | 綿柎開,天地始粛,禾乃登 |
| 白露 | 9月7日 | 草露白,鶺鴒鳴,玄鳥去 |
| 秋分 | 9月23日 | 雷乃収声,蟄虫戸,水始涸 |
| 寒露 | 10月8日 | 鴻雁来,菊花開,蟋蟀在戸 |
| 霜降 | 10月23日 | 霜始降,霎時施,楓蔦黄 |
| 立冬 | 11月7日 | 山茶始開,地始凍,金盞香 |
| 小雪 | 11月22日 | 虹蔵不見,朔風払葉,橘始黄 |
| 大雪 | 12月7日 | 閉塞成冬,熊蟄穴,魚群 |
| 冬至 | 12月22日 | 乃東生,麋角解,雪下出麦 |
| 小寒 | 1月5日 | 芹乃栄,水泉動,雉始 |
| 大寒 | 1月20日 | 款冬華,水沢腹堅,始乳 |
まとめ
縦書きにすると左右対称になり、それで鬼を混乱させて除けるという立春大吉……とてもユーモアがあって、実践してみたくなります。
あまり馴染みがなかったという方もこれからは立春大吉のお札を貼ってみるといいかもしれません。
いい1年になることでしょう。
スポンサードリンク