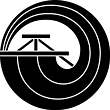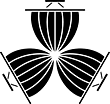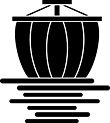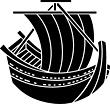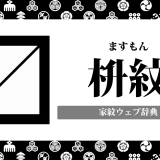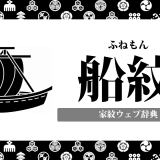「船」はかつてから人々の移動手段の一つでした。その船の「帆」は、舵をきるための大切な部分です。
帆をモチーフとした「帆紋」は、「船紋」とはまた別に存在し、海関連の家々で用いられていました。
今回は、「帆紋」の意味・由来・種類などについてご紹介いたします。
スポンサードリンク
|
|
|
帆紋の意味・由来とは?

| 読み方 | ほもん |
| 家紋の分類 | 器物紋 |
| >>家紋辞典で他の家紋もチェック<< | |
帆とは船の舵をための帆のことで、家紋としては船そのものとは区別され、帆をメインに描かれています。
見てすぐに船の帆とわかるデザインのものが多く、海関連の家の紋に用いられていました。これには「航海を祈願する想い」が込められていたとされています。

たいては船の全体像は描かれず、帆のみがモチーフとなっていますが、中には「帆掛け船」など全体が描かれたものもあります。
名字が船に関係している船戸氏や船村氏、布施氏や大井氏などが使用しました。
スポンサードリンク
帆紋の種類いろいろまとめて解説
|
一つ帆巴 |
三つ帆の丸 |
三つ寄せ真向き帆 |
五つ帆の丸 |
|
糸輪に真向き帆 |
霞に帆 |
帆掛け船 |
真向き帆掛け船 |
帆紋は、帆をメインとして船全体はあまり描かれなかった特徴があります。また、「一つ帆巴」のように1枚の帆で描かれたものもあれば、「三つ帆の丸」「五つ帆の丸」のように複数枚の帆を描いたものなど、枚数は様々でした。そして、複数で描かれたもののほとんどは円形になっています。

また、他の紋と組み合わせたものには「糸輪に間向き帆」「霞に帆」などがあり、ぼんやりとした波模様を「霞」で表した家紋でした。
「霞紋」は戦国時代に用いられていたとされていますが、具体的な使用例はあまり残っておらず、あまりポピュラーな家紋ではありまん。
詳しくはこの記事をチェック!
スポンサードリンク
帆紋の中には、船全体を描いた珍しいデザインのものもあります。「帆掛け船」「間向き帆掛け船」はその例で、「船紋」にも見えますが帆紋に分類されるものとなっています。
「船紋」と「帆紋」はどう違うの?

帆は船にあるものなのに、家紋ではそれぞれが独立していた区別されているのが不思議ですよね。
帆紋は「帆のみ」が描かれているのに対し、船紋は「船全体」が描かれているといった違いがあります。
船紋には様々な船の様子を表現したデザインが多数ありますので、是非下記の別途記事で船紋についてチェックしてみましょう!
詳しくはこの記事をチェック!
スポンサードリンク
まとめ
船の帆を描いた「帆紋」についてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?
「船紋」がある中、船の一部である帆をまた別の紋として使用していたのには、海関連の家の意向あってのことだったのでしょう。
船紋について合わせて知ると更に面白いですので、是非合わせて船紋の記事もチェックしてみてくださいね。
スポンサードリンク